高崎経済大学では、2025年度も「特別講義」シリーズがスタートしました。本シリーズは、学生が“自分らしく生きる力”を育むことを目的とした実践型のプログラムであり、単なる知識の伝達にとどまらず、自己理解・対話・行動を通じて人生を主体的に設計するための学びを重ねていきます。
4月8日に配信された第1回講義では、「世界と日本の未来を考える2.0」というタイトルのもと、講義全体の設計意図や背景が共有されるとともに、受講生一人ひとりが“自分自身の可能性”と出会うための導入的な内容が展開されました。
講義のねらいと設計思想
「世界と日本の未来を考える2.0」は、“自己実現”と“社会との接点”をテーマに据えた探究型の特別講義です。講義の冒頭では、進行を務める野口(Vision Connect合同会社代表)から、講義が目指す世界観と背景にある社会課題について、熱量を持って語られました。
本講義の最大の特徴は、「キャリア教育」や「起業マインド」の習得を目的とするのではなく、まず“自分とは何か”という問いに正面から向き合うことにあります。講師陣は、これを「自己認識→自己開示→自己表現→自己実現」という段階で整理しており、学生が自分自身を言葉にし、他者と共有し、社会に対して表現していくプロセスを丁寧に支援していく設計となっています。
授業の中では、「もはや社会には“正解”が存在しない」という現代の特徴にも言及されました。これからの時代においては、決まった道をなぞるのではなく、自分の価値観や関心に基づいて“問い”を立て、それに向かって行動していける力――すなわち「ビジョンを持って生きる力」が求められていると強調されました。
このような背景のもと、講義では「価値観の明確化」「ビジョンの言語化」「自分軸と社会軸の接続」という3つの柱を軸に、毎回テーマとワークを設定。単にキャリア形成を語るのではなく、人生そのものをどう設計していくかという“土台づくり”から着手する構成となっています。
初回授業の構成
今回の初回授業はオンデマンド配信形式で実施され、プログラム全体の構成説明と、講師陣からの熱意あるメッセージによって幕を開けました。
冒頭では、進行役の野口と石川(いずれもVision Connect合同会社共同代表)による対話形式のプレゼンテーションが展開され、学長・水口氏も特別講義の総合プロデューサーとして登場。軽快な掛け合いの中に、本講義が掲げる「幸せに生きる力とは何か」という本質的な問いが投げかけられました。
野口は、「幸せになることは簡単ではない。だからこそ、自分の価値観やビジョンを明らかにし、自分自身の力で人生を切り拓く“起業家マインド”が求められる」と語ります。自身のキャリア上の転機や、大企業からの独立・ベンチャー起業の経験を交えながら、「自己実現の力」がどのように社会と接続していくかを具体的に示しました。
また、講義全体のねらいとして、「まず自分を知る(自己認識)ことから始まり、他者や社会とつながることで自己表現・実現へと至る構造」が提示されました。この一連のプロセスが、「自己効力感の獲得フロー」と重なることも紹介され、学生にとっての実践的な指針として示されました。
初回はインプット中心の内容でしたが、今後の授業で行われるワークの意義や進め方にも触れられました。学生は、価値観やビジョンを探る個人ワークを通じて、“社会”と“自分”のあいだにある接点を言語化し、将来的な行動につなげていくことが期待されます。
多様なロールモデルとの出会い
本講義の大きな特徴のひとつが、第一線で活躍する多彩なゲスト講師との出会いを通じて、“自分とは異なる価値観”に触れる機会が設けられていることです。初回授業では、そのラインナップが紹介され、受講生の期待感を大きく高める内容となりました。
登壇予定のゲストは以下の3名です。
- 木寺 祥友 氏(株式会社エル・カミノ・リアル代表取締役/社団法人Rubyビジネス協議会 顧問)
JavaやAndroidの黎明期から開発に携わり、日本のIT業界を支えてきた人物。数々の政府系・民間プロジェクトで要職を歴任し、現在もデジタル領域のコンサルタントとして活躍しています。「高経生よ、起業家になれ」と題し、変化の激しい社会において、価値を生み出す人材になるための視座を提供します。 - 大橋 由香 氏 (店主/料理研究家(YouTuber)/他企業経営)
“好き”を原点に、自分の軸を貫いてキャリアを切り拓いてきた女性起業家。SNSでの発信からスタートし、現在は会社経営、レシピ本出版、テレビ出演など、多方面で活躍中です。等身大の視点で「自分らしさとは何か」を語り、受講生との対話も重視した講義が予定されています。 - 世良 拓也 氏(国内大手IT企業データサイエンティスト/Neko Hackerトラックメイカー)
大手メーカーで生成AIの研究開発に従事する一方、音楽ユニット「Neko Hacker」のメンバーとしてアーティスト活動も展開。異なるキャリアを同時に歩む“パラレルキャリア”の実践者として、自分の才能や関心を複数の形で表現する生き方を紹介してくれます。
このように、異分野・異世代・異なる価値観を持つゲスト講師との出会いを通じて、学生は「こうでなければならない」という思い込みを揺さぶられ、多様な人生の可能性に触れることになります。講師陣は、「正解のない時代だからこそ、自分にとっての“納得解”を探す旅を始めてほしい」と語っており、この講義がその出発点になることを目指しています。
卒業生が語るリアルな変化
今回の初回講義では、過去に本プログラムを受講し、現在は独立して事業を手がけている卒業生・溝渕さんがゲストとして登壇しました。学生の視点から講義を振り返る姿は、受講を検討している学生にとって、非常に現実味のあるメッセージとなりました。
溝渕さんがこの講義に出会ったのは、大学1年次の後期。当時は「大学生活をどう過ごしていくか」が見えず、漠然とした不安を抱えていたといいます。そんな中、「世界と日本の未来を考える」という一見大きすぎるテーマに戸惑いながらも、登壇者たちのリアルな体験談に触れることで、「この人たちも最初は悩みから始まっていたんだ」と感じたことが、自己理解への第一歩になったと語ってくれました。
特に印象的だったのは、「授業を受けた直後は、正直何も変わらなかった」という率直な言葉です。しかし、講義で繰り返し問われた「あなたは何を大切にしたいのか?」という問いが、時間をかけてじわじわと自分の中に浸透していき、結果的に大学在学中に“自分で事業を起こす”という進路を選択する原動力になったとのことでした。
この発言は、本講義が“すぐに役立つ答え”を提供するのではなく、時間をかけて自己と向き合う“問いの種”を蒔く授業であることを示しています。溝渕さんは、「この授業はNetflixのようなもの。面白そうと思ったら一歩踏み出してみて。期待しすぎず、でも心を開いて受けることで、きっと何かが残る」と、後輩たちへ温かいエールを送りました。
学びを支える講義設計と評価方法
本講義では、全15回の授業を通じて、学生が自己理解から自己表現、そして行動へと至るプロセスを段階的に踏んでいく構成となっています。特に印象的なのは、知識の習得よりも「自分の考えを深めること」「問いを持ち続けること」を重視している点です。
評価方法もこうした理念に即して設計されており、成績は出席と最終的な自己表現シート(※ビジョンや価値観を言語化するワークシート)によって行われます。講義内で課されるテストやレポートはなく、「日々の学びを自分の内面にどう落とし込むか」という“内的プロセスの可視化”が重視されます。
また、各回の講義では対話型のワークやゲストとのQ&Aセッションが多く取り入れられ、学生が自分の言葉で考え、自分のペースで学べる設計がなされています。例えば、価値観カードを使ったワークや、自分の「ビジョン」を描くためのキャンバス作成、講師や仲間との対話によるフィードバックセッションなど、体験的な学びを通じて自己理解を深めていく構成です。
このように、学生一人ひとりの“今”に寄り添いながら、「自分らしい生き方」とは何かを考え抜く時間が丁寧に用意されています。講師陣からは「無理はしなくていい。ピンときたタイミングで、自分なりに一歩を踏み出してくれればいい」といった声もあり、学生の主体性を尊重した教育姿勢を心がけています。
学生が得る三つの学び
この講義が目指すのは、単なるキャリア支援ではなく、学生一人ひとりが「人生の土台」をつくることです。そのために設計された学びの過程には、以下の3つの大きなテーマがあります。
① 多様なロールモデルとの出会いによる“視野の拡張”
学生たちは、第一線で活躍する社会人講師や起業家との対話を通じて、自分の想像を超えた生き方や働き方に触れることができます。「こんな人生もあるのか」「こんな価値観で生きている人がいるのか」といった驚きや共感が、既存の枠組みを超える“思考の柔軟性”を育てていきます。
② 正解のない問いと向き合う“自己探究の姿勢”
本講義では、「あなたは何を大切にして生きていきたいか?」「10年後、何をしていたらワクワクするか?」といった問いが繰り返し投げかけられます。明確な正解がないからこそ、思考の“定点観測”を重ねることが重要です。自分の言葉で考え、他者と共有し、また考え直す――このプロセスそのものが、自己認識の深化につながります。
③ 小さな行動変容を積み重ねる“実践力”
最終的に目指すのは「行動する人になること」です。講義では、毎週のリフレクションやワークシートを通じて、自分の変化を可視化しながら、小さな一歩を着実に積み上げていきます。卒業生のように、「すぐには変わらなかったけれど、問い続ける中で進路選択や価値観に影響を与えた」という実践例は、この講義が“じわじわと効く”学びであることを物語っています。
このように、知識の伝達ではなく、価値観の揺らぎや問いの再構築を促すことで、学生自身が“自分の人生を自分の言葉で語れるようになる”――それが、この講義が目指す最大のゴールです。
今後の展開と社会との接点
本講義は、単なる「15回の授業」で完結するのではなく、学生の人生に長期的な問いを残す“プロセス型の学び”として設計されています。4月15日からは対面形式の講義がスタートし、ゲスト講師の講演や、学生同士の対話を通じた体験型ワークが本格化していきます。
講義後半では、「価値観の言語化」「ビジョンの可視化」「行動のトライアル」を支援する時間が設けられ、最終回では学生一人ひとりが自己理解をもとにまとめた“表現シート”を共有します。このシートは単なる提出物ではなく、自分の変化の軌跡を見つめ直す定点観測として活用される予定です。
また、講義の透明性と対外的な連携を重視し、学外関係者や教育関係者に向けたフィードバック会やオープンセッションも検討されています。大学としても、学内に閉じた活動ではなく、「社会に開かれた学び」を実践していく姿勢が示されています。
本講義が育もうとしているのは、「社会課題を他人事にせず、自分ごととして引き受ける力」です。講師陣が一貫して語っているのは、「自分軸を見つめ直すことが、やがて社会とつながり、社会を変えていく原動力になる」という信念でした。
“正解のない時代に、自分の問いを持って生きる”――この価値がますます求められる今、学生一人ひとりがこの講義を通じてどのような“問い”を手にするのか。その過程こそが、本講義の何よりの成果であり、社会への最大の接続点となっていくことでしょう。
今後の展開にも、ぜひご期待ください。

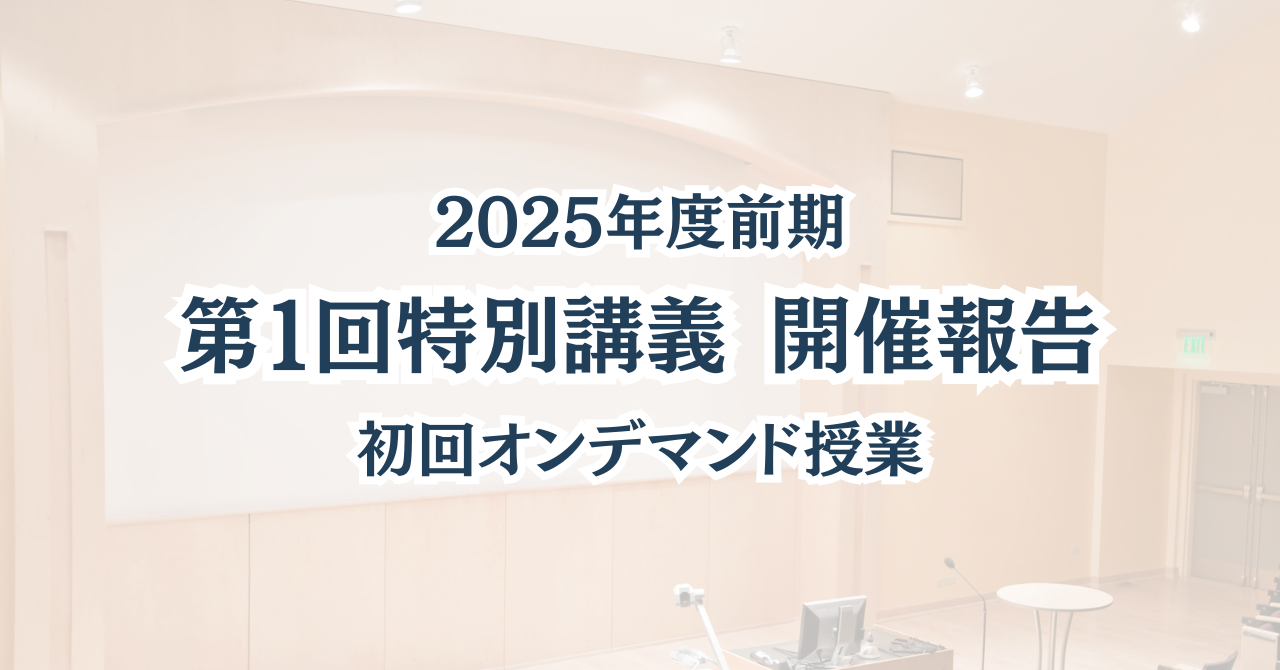
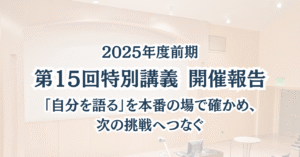
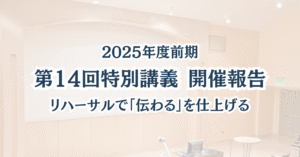
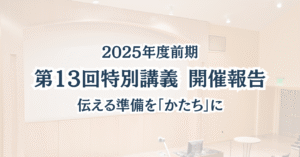
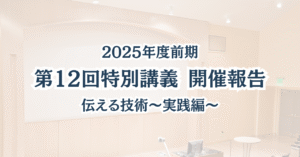
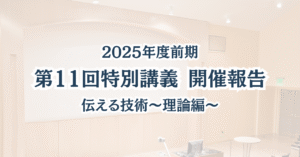
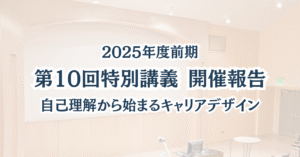
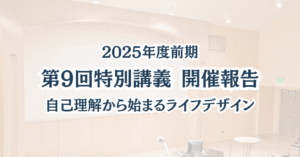
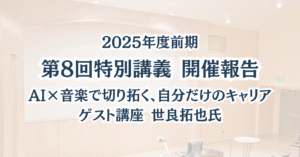
コメント