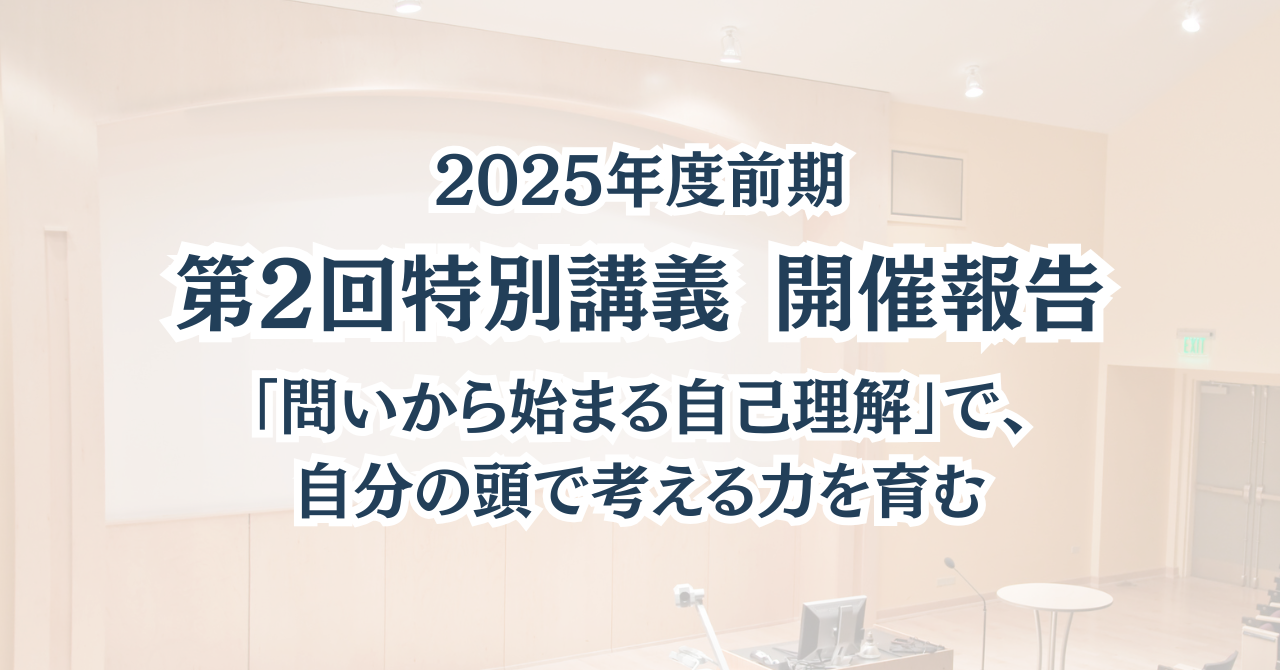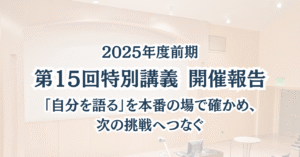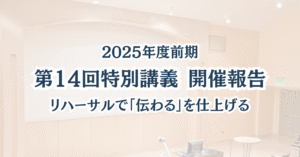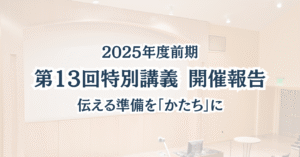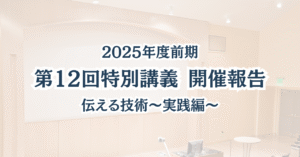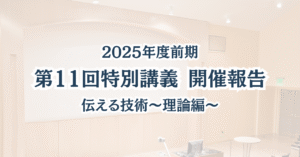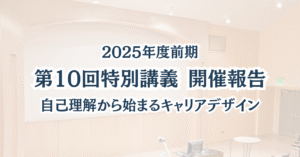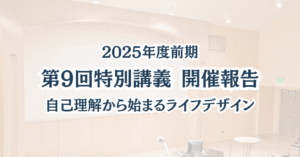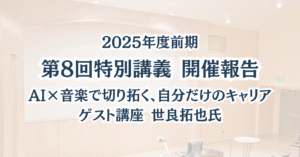高崎経済大学では、2025年度も「特別講義」シリーズを開講しており、全15回のうち第2回目の講義が4月23日 2限目に実施されました。
本シリーズは、学生が「自分らしく生きる力」を育むことを目的としたプログラムであり、単なる知識の習得にとどまらず、思考・内省・対話のプロセスを通して、主体的に学び続けるための土台づくりを目指しています。
第2回目のテーマは「問いから始まる自己理解」
導入ではあえて「雑談から始めましょう」と切り出し、講義の本質が“正解探し”ではなく“自分で考えるプロセス”であることを伝えました。問いを軸にしながら、人生・世界・仕事の意味を考え、学生たち一人ひとりの内側にある「自分軸」に出会っていく時間となりました。
「今日はまず雑談から」—問いを通じて“自分の頭で考える”スイッチを入れる
第2回特別講義は、あえて「今日はまず雑談から始めましょう」という言葉でスタートしました。
これは、学生が“答えを当てる”モードではなく、“自分の頭で考える”モードに切り替えられるようにするための、野口からの最初の仕掛けです。
教室の空気がほぐれたところで、私たちはこう問いかけました。
「この講義をなぜ履修したのですか?」「何を求めてここに来ましたか?」
一見シンプルな問いですが、学生たちの中からは次々にリアルな声があがりました。
- 「大学4年間をどう過ごすか悩んでいて、何かヒントが欲しかった」
- 「社会で活躍している人の話を聞いて、自分の将来像を考えるきっかけにしたい」
- 「“自分らしさ”って何なのか、まだよく分からないから考えてみたい」
このように、自分の目的を言葉にすることが、講義全体を“自分ごと”として受け止める第一歩となりました。
「人生・世界・仕事とは何か?」深い問いに、自分の言葉で向き合う時間
今回の講義の核心となったのは、「人生とは何か」「世界とは何か」「仕事とは何か」といった、日常ではなかなか立ち止まって考えることのない“深い問い”に向き合う時間でした。
一見すると抽象的で難しそうなテーマではありますが、導入ではまず「2分間、自分で考える」→「隣の学生と2分間で共有する」というステップを取り入れ、心理的ハードルを下げながら徐々に対話の輪を広げていきました。
「人生とは何か?」——自分の軸を探る問い
この問いに対して、学生からはこんな言葉が生まれました:
「人との関わりを通して、自分を知ること」
「自分で選び続けることが人生なのかも」
「“今ここ”を感じることが、生きているってことかなと思いました」
「世界とは何か?」——視点を広げる問い
このテーマでは、学生たちの思考の多様性が際立ちました。
「自分の見ている世界って、ほんの一部だと気づいた」
「自分がどう関わるかで、世界の見え方も変わる気がした」
“世界”という漠然とした言葉が、身近な感覚や体験と結びついたとき、学生たちは一人ひとりの視点から現実を捉え直していました。
「仕事とは何か?」——未来を考える問い
この問いは、特に「正解がありそうで実はない」テーマとして、学生たちを悩ませつつも深く引き込んでいきました。
「今までは“安定した職業に就くこと”がゴールだと思っていたけど、“誰かの役に立てるか”って視点があるのは新鮮だった」
「仕事は手段じゃなくて、“自分らしさ”を表現する場所にもなるのかも」
「親の影響が強かったけど、改めて“自分のための仕事”を考えたくなった」
やる気のしくみを捉え直す
――「テンション」と「モチベーション」の違いを知る
講義では仕事の問いに関連して、「どうやって長く続くやる気を持ち続けられるか」という話がされました。
野口は、やる気の正体を「テンション」と「モチベーション」という2つの概念に分けて解説しました。
テンションとは、一時的・瞬間的に高まる気分や勢いのようなもので、声を出す、体を動かす、盛り上がるなど、外的な刺激によって一気に上げることができます。
一方で、持続性がなく、何かトラブルが起こったり気分が沈んだりすると、一気に下がってしまうという特性があります。
それに対して、モチベーションは長期的なやる気の源泉であり、「外発的モチベーション」と「内発的モチベーション」に分けられます。
前者は、報酬や評価、地位など外から与えられる要因によって動かされるやる気、後者は、自分の内側にある「やりたい」「意味がある」「自分にとって大切」といった納得感から生まれるやる気です。
講義では、特に内発的モチベーションの重要性が強調されました。
「自分が何をやりたいか、自分にとって何が大事か」(=自分軸)を引き出し、そこから行動を設計していくことで、やる気は自然と湧いてくる。しかもそれは長期的に持続し、結果にも結びついていく」
こうしたモチベーションの構造理解は、単なる気合いや根性に頼るのではなく、自分の内側から行動の根を育てていく視点として提示されました。
自分のやる気のスタイルを知る
――「ビジョン型」と「価値観型」の2つのアプローチ
やる気に関する構造的理解のあと、講義では「ビジョン型」と「価値観型」という、
行動の源泉に関する2つのスタイルが紹介されました。
ビジョン型とは、未来の理想像や目標(ビジョン)を明確に描き、
そこから逆算して現在の行動を設計していくタイプ。
「将来こうなりたい」「5年後にはこうありたい」という具体的な姿を想像できる人にとっては、このスタイルがやる気を高める軸となります。
一方、価値観型とは、未来のビジョンが描きづらい、あるいは明確に決めると逆に気持ちが重くなる人に向いたスタイルです。
この場合は、「自分が大切にしたい価値観」や「過去の充実感の記憶」を起点として、行動の意味や方向性を見出していきます。
講義では、旅行を例にとり、
- 「〇〇に行きたい」と目的地から考えるのがビジョン型、
- 「ゆっくりしたい」「地元の料理が食べたい」と理由から考えるのが価値観型、
という対比を通して、自分に合ったスタイルを把握する重要性が伝えられました。
両者には優劣があるわけではなく、どちらも“自分らしいやる気”を引き出すためのヒントとなるものであり、
講義では「自分に合ったスタイルを知ることが、持続可能な行動の出発点になる」という考えが示されました。
“あなたの名前で生きる”
今回の講義の締めくくりとして、野口が紹介したのは、ある友人の実話でした。
その人物は、誰もが知る安定した大企業に勤めながらも、「自分のビジョンを実現したい」という想いを胸に、数年後に思い切ってベンチャー企業へと転職。
社会的な肩書きや安定を手放し、“自分の名前”で勝負する道を選んだ一人の生き方が語られました。
肢」として再定義し直す姿も見られました。
このストーリーを最後に紹介した理由は、誰かの選択の“リアル”が、自分自身の問いを動かす強力な触媒になると信じているからです。
正解のない時代だからこそ、目の前の問いに向き合いながら、「自分の名前で生きるとはどういうことか」を、それぞれの言葉で考えてもらえたら――。その願いを込めて、講義は幕を閉じました。
今回の第2回講義では、「人生」「世界」「仕事」といった根源的な問いを通して、
学生一人ひとりが自分の内側と向き合い、“自分で答えを出す”という感覚に触れる時間となりました。
今後の講義では、いよいよ多様な社会人講師を迎えながら、
さまざまな職業や価値観、生き方に触れていくフェーズに入っていきます。
社会で実践を重ねてきた人々との対話を通して、
「自分だったらどうするか」「どんなふうに働き、生きていきたいか」といった問いが、より具体的に、より身近に立ち上がってくることが期待されます。
講義はまだ始まったばかりです。
これから続いていく学びのプロセスの中で、学生たち一人ひとりが「自分の言葉で、自分の人生を語れるようになる」ことを目指し、私たちも伴走していきます。