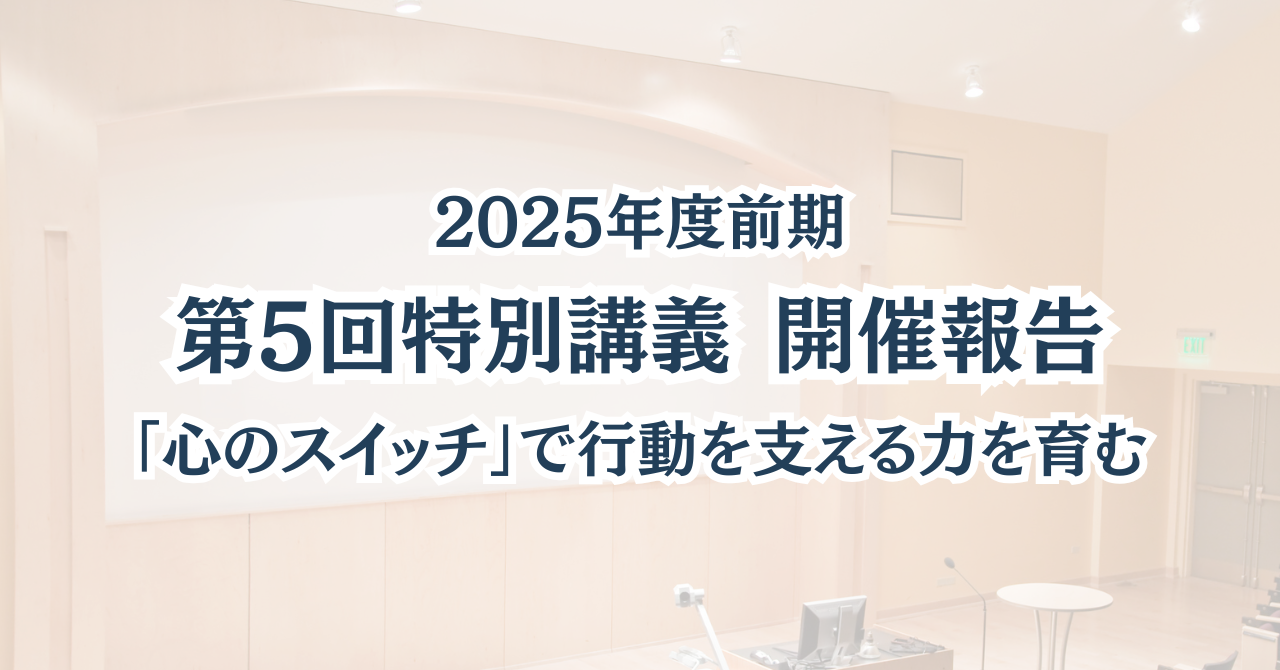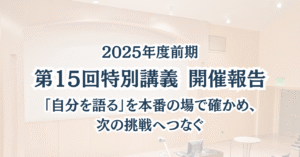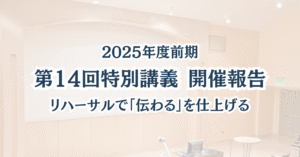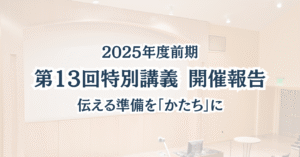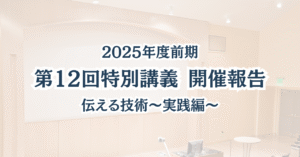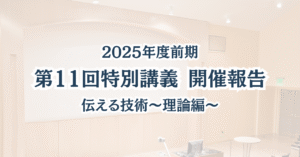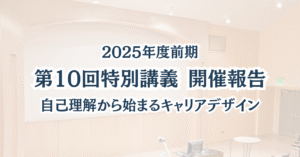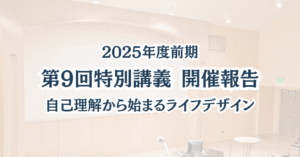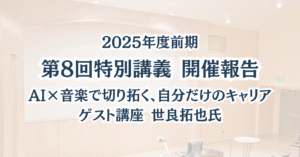高崎経済大学では、2025年度も「特別講義」シリーズを開講しており、全15回のうち第5回目の講義が5月20日 2限目に実施されました。
本シリーズは、学生が「自分らしく生きる力」を育むことを目的としたプログラムであり、単なる知識の習得にとどまらず、思考・行動・対話のサイクルを通して深い自己理解と実践力を養っていくことを目指しています。
第5回目のテーマは「心のスイッチ」
これまでの講義で扱ってきた“志”や“価値観”をベースに、「いかに自ら行動を起こすか」「行動を支えるためにどのように心を整えるか」に焦点が当てられました。講義では、学生一人ひとりが自身の状態を可視化し、行動と感情の関係性を体感的に学ぶワークを中心に展開されました。
ワーク①身体を使って「自分の現在地」を知る
――成長の3段階を空間で表現するワーク
この講義では、最初に「自分はいま、どのような心理的な状態にあるか」を見つめ直すためのワークが行われました。単なる内省ではなく、教室という空間を「心の成長段階」に見立て、実際にその場所に身体を動かして立つという、体感的な手法が用いられました。
講師・野口が提示したのは、「成長の3段階モデル」です。学生たちは、以下のいずれかに当てはまると感じたポジションへ、自らの判断で移動していきます。
- マイナス:まだ行動に移せず、内面でも苦しさや不安がある状態
- ゼロ:特別な不満はないが、目的意識や強い意志を感じられない状態
- プラス:やりたいことや目標が少しずつ見えてきて、行動の準備が整ってきた状態
- モア:明確な志や目的を持ち、すでに積極的に行動を始めている状態
野口は教室内の段差やステージを活用し、物理的な高さをポジションの象徴として可視化。学生たちは、配布されたワークシートで自身の状態を記述したのち、実際に席を立ち、該当する場所へ移動します。さらに、その場所で数人ずつグループを作り、「なぜそのポジションを選んだのか」を対話形式で共有する場が設けられました。
この活動により、学生は「自分の心の位置」を“頭”だけでなく“身体”と“他者との比較”を通じて再確認することができました。
「紙に書くだけではわからなかった自分の状態を、場所として感じられた」
「人と違う場所に立つことが最初は怖かったが、“これが今の自分”と受け止められた」
といった声もあり、自己理解と自己受容のきっかけとして有効なワークとなりました。
ワーク②「ポジティブな状態の再現」
――姿勢・表情・呼吸で心を“上書き”する体験ワーク
前半のポジションワークを通して自分の現在地を把握した学生たちは、次に「行動につながる心の状態」を自らつくる方法を学びました。
このワークでは、「良い状態=心が前向きだった瞬間」を身体的に再現することを目指し、体の使い方によって心を整える力を体感的に身につけます。
野口が伝えたのは、「心と体は密接につながっており、体から心を変えることができる」という原則です。
Step 1|過去の“自分らしくいられた瞬間”を思い出す
まず学生たちは、自身の過去を振り返り、「嬉しかった時」「達成感を得た時」「気分が上がっていた時」などのシーンを1つ選びます。
それは特別な成功体験である必要はなく、「友人と笑い合った昼休み」「天気が良くて気分が晴れた登校時」など、ちょっとしたポジティブな瞬間でも構いません。
選んだシーンをもとに、次の3点をワークシートに記入します:
- そのときの姿勢はどうだったか?(例:背筋が伸びていた/胸を張っていた)
- 表情はどんな様子だったか?(例:自然と笑顔だった/目が開いていた)
- 呼吸はどんな状態だったか?(例:深くゆったり/弾むような浅い呼吸)
Step 2|ペア・グループで“再現して見せる”
次に、そのポーズを実際に全身を使って再現してみるワークへと進みます。
学生たちはグループ内で1人代表を決め、他のメンバーの前で「そのときの自分」を姿勢・表情・呼吸で表現します。周囲の学生たちは、「もっと笑顔にしてみては?」「呼吸が浅いかも」などとフィードバックを交わし合いながら、その人に合った“最適なポジティブポーズ”を探っていきます。
野口からは、「人によって“自然体”の表現は異なる」との補足もあり、単なる見た目の演技ではなく、内面の状態を引き出すための姿勢づくりを意識するよう促されました。
2つ目のワーク「ポジティブな状態の再現」を終えて、学生からは
「思ったより自分の動きが小さかったことに気づいた」
「ポーズをとるうちに本当に気分が上がってきた」
「体を変えると、思考や言葉も前向きになって、実は」
といった感想があり、普段あまり意識しない“無意識の身体の習慣”に気づく貴重な機会となりました。
このワークは、アスリートや俳優、モデルなどが活用している「身体から感情をコントロールする」手法を、学生にもわかりやすく翻訳したもので、緊張や不安を乗り越えたい場面でも活用できる“再現可能なコンディショニング技術”として紹介されました。
ワーク③ 自分の頭の中にある“言葉”と向き合う
――セルフトークを可視化し、思考の癖を知るワーク
「体を使って心を整える」ワークの後、学生たちは“心の中で自分にかけている言葉=セルフトーク”に焦点を当てたワークに取り組みました。
これは、無意識に巡っている言葉が、自分の行動や判断、気分に大きな影響を与えていることを実感し、その癖に気づくことを目的としたワークです。
Step 1|頭の中に“こだましている言葉”を書き出す
野口からの最初の問いかけはこうでした。
「高校時代の自分、大学に入ったばかりの自分、そして数年後の社会人になった自分に思いを馳せたとき、あなたの頭の中にはどんな言葉がこだえますか?」
学生たちは配布されたワークシートに、頭に浮かんだ言葉をそのまま“言語化”して書き出すという作業に集中します。
「できる気がしない」「頑張らなきゃ」「もっとちゃんとしなきゃ」「自分なんて」……
最初は言葉が出てこなかった学生も、時間が経つにつれて、次々と浮かぶ“自分との内なる対話”をノートに書き連ねていきます。
Step 2|ネガティブな反復と、問いかけの力を知る
野口からは、人間が1日に行う思考は約6万回、そのうち8割近くがネガティブな内容であるというデータも紹介されました。これは、生物が生き残るために危険を回避する“防衛本能”として備わっている機能ですが、現代社会ではしばしば「チャレンジを阻む内なる声」として働いてしまいます。
ポジティブな言葉を無理に繰り返すのではなく、野口が強調したのは「問いかけの力」です。
「本当はどうなりたいのか?」
「なにを大切にしたいのか?」
「どうしたら前に進めるのか?」
こうした“前向きな問い”を自分に投げかけることで、脳のフォーカスが変わるといいます。
このワークを終えた後、学生たちからは以下のような感想がありました:
「普段、無意識に自分に厳しい言葉ばかり投げていたことに気づいた」
「問いを立てるだけで、頭の中が整理された気がした」
「結果に振り回されず、自分の声を聞こうと思えた」
このプロセスは、「心のスイッチ=行動を起こすための内的エネルギー」を得るために不可欠な“言葉のリセット”の練習であり、ネガティブな自動思考からの脱却を目指す力強い第一歩となりました。
ワーク④ 意識の向け方を変える
――“見るもの”が変われば、世界の見え方が変わる体験ワーク
講義の終盤では、「心のスイッチ」の締めくくりとして、“意識の向け方”を体感するワークが行われました。
このワークは、「人は、見たいものだけを見るようにできている」という脳の特性を理解し、物事の捉え方や行動選択の前提となる“フォーカスの力”に気づくことを目的としています。
Step 1|視覚の焦点化を体感する
まず学生たちは目を閉じた状態で着席し、野口の合図で目を開けると、
「15秒間で、周りにある青いものをできるだけたくさん探してください」
という指示が出されます。
一斉に教室を見回し、青色の本、ペン、服、ポスターなどに視線を走らせる学生たち。15秒後には再び目を閉じ、野口から問いかけがあります。
「では、赤いものはどこにありましたか?」
突然の質問に戸惑う学生たち。青を必死に探していたため、赤い物体の記憶がほとんど残っていないことに、多くの学生が驚きをもって気づきました。
Step 2|意識をどこに向けるかは“自分で決められる”
このワークを通して、野口が伝えたメッセージは明確でした。
「自分が何に意識を向けるかによって、世界の見え方がまったく変わる」
「見たいものだけを見て、他の大切なことを見落としてしまうことがある」
たとえば、結果が悪かったときに「何がダメだったか?」ばかりを見ようとすれば、ネガティブな材料ばかりが目に入ってきます。一方で、「何がうまくいっていたのか?」「どこに可能性があるのか?」に意識を向ければ、前に進むための情報が自然と目に入るようになります。
野口はこれを「フォーカスの転換」と表現し、自らの意識の向け方を選び取ることが、“自分らしい行動”の起点になると説明しました。
「自分の世界が“選んで見ている”ものに影響されていると気づいた」
「もっと良いものに目を向ける練習をしたいと思った」
「ネガティブなことを考えそうになったとき、フォーカスを変える問いを立ててみたい」
このワークを通じて、学生たちは日常生活においても、「見るものを選ぶ」意識を持つことで、自分の感情や行動に主体性を取り戻せるという学びを得ていました。
自分の“整え方”を持つことが、変化の第一歩になる
講義の最後には、「人は誰かに言われて変わるのではなく、自分で“変わりたい”と思ったときに初めて動き出せる」というメッセージが学生たちに共有されました。
野口は、自身の体験をもとに、心が不安定な時期にも支えとなったのは、自分自身の“内なる声”を聞こうとする姿勢だったと語ります。
この日の講義は「心のスイッチ」というタイトルでありながら、実際には“勢いよくスイッチを入れる方法”よりも、その前段階となる「リセットする力」「整える力」を丁寧に扱う内容となっていました。
このことが、かえって多くの学生にとって「無理なく行動に向かえるきっかけ」となり、変化のスタート地点を自分で選び取る感覚へとつながったようです。
今回の講義を通して、学生たちは「何かを成し遂げる」以前に、「自分の状態に気づき、それに合った準備をすることの大切さ」を実感しました。
この“行動の前提”を整える学びは、学業や就職活動はもちろん、これからの人生の様々な選択においても重要な基盤となっていくことでしょう。
特別講義シリーズは、今後も「志の育成」「キャリアデザイン」「行動のデザイン」といったテーマを軸に、学生の内面と行動の橋渡しを行っていきます。
次回第6回講義では、これまでの「大事なこと」に続き、「得意なこと」「好きなこと」をテーマに、より深い自己理解に取り組みます。学生一人ひとりの“志”の核を見つけていくプロセスが、いよいよ本格化していきます。