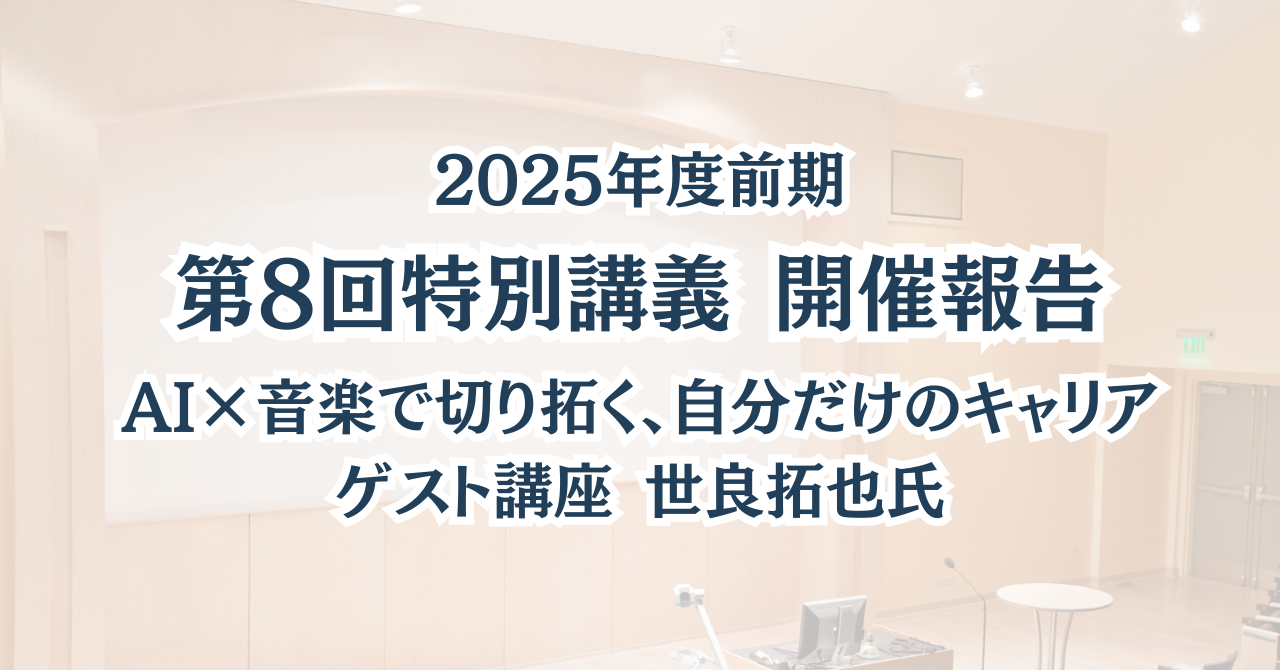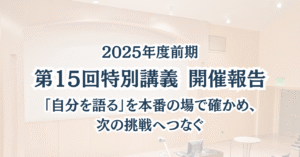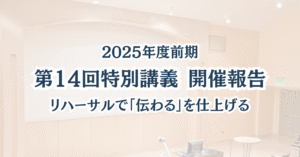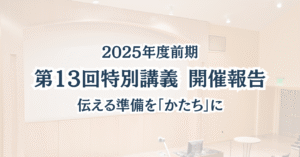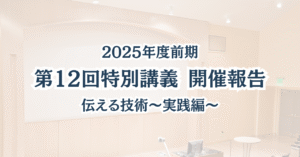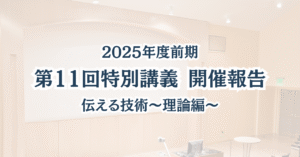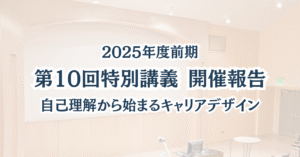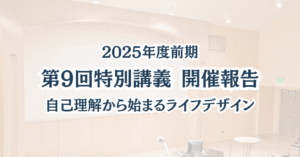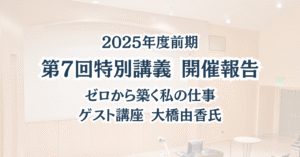高崎経済大学では、2025年度「特別講義」シリーズの第8回目の講義が実施されました。
本シリーズは、学生が「自分らしく生きる力」を育むことを目的としており、社会で活躍する多彩なゲストの話を通じて、自己理解や価値観の探究、キャリア形成のヒントを得ることを狙いとしています。
第8回目となる今回は、「AI時代を生きる技術と芸術のパラレルキャリア」をテーマに、国内大手IT企業でAIの実用化を担うデータサイエンティストでありながら、音楽ユニット「Neko Hacker」としても活動する世良拓也氏をゲストに迎えました。
世良氏は、「2つの仕事」を軸に、「好きなことを続ける力」「掛け算でつくる自分の居場所」「環境に応じて変化する自分の役割」などを語り、学生に新しいキャリアの捉え方を提示しました。
キャリアの原点 ― 好きなことを仕事にするまで
講義の前半では、世良氏が現在のキャリアに至るまでの歩みが、学生たちに向けて率直に語られました。大学時代、AI技術に興味を持ち始めたことがきっかけで、卒業後は国内大手IT企業に入社。以来、データサイエンティストとして、AIの社会実装やサービス開発に携わるようになります。
一方で、学生時代から音楽にも強い関心を持っていた世良氏は、メタルバンドでギターを担当した経験や、自主制作での作曲活動を通して、音楽表現の面白さにも魅了されていきました。当初、AIと音楽はまったく別の領域として扱っていたそうですが、次第に「この2つを掛け合わせることで、自分にしかできない表現ができるのではないか」という気づきを得るようになります。
こうして、平日はAIの専門家として業務に取り組みながら、週末や夜には音楽ユニット「Neko Hacker」の一員として、作曲やライブ活動を行うという“パラレルキャリア”のスタイルが形づくられていきました。世良氏は、「どちらか一方を諦めるのではなく、どちらも続けたからこそ、唯一無二の道が開けた」と振り返ります。
AIと音楽——一見交わらないように見える2つの世界を貫くのは、「面白いと思ったことを追求し続ける姿勢」です。この“好き”を出発点とするキャリアの原点が、講義全体を通して学生たちの関心を強く引きつけていました。
自己認識 ― 好きなことを続けて見えた自分
講義の中盤では、世良氏がキャリアを重ねる中で「自分が本当にやりたいこと」に気づいていったプロセスが紹介されました。AI技術を社会の課題解決に役立てるさまざまなプロジェクトに携わるなかで、次第に明確になってきたのは、「AIの可能性や面白さを、もっと多くの人に伝えたい」という自身の思いでした。
たとえば、チョコレートの味をAIで分析し、その結果をもとに新たな製品開発に活かすプロジェクトや、障がいのある方も直感的に音楽を演奏できる楽器の開発など、単に技術を追求するだけでなく、“人に寄り添い、人を助ける”視点でAIを活用する取り組みに深く関わってきた世良氏。その一つひとつの経験が、自分の根底にある動機を浮かび上がらせてくれたといいます。
また音楽活動においても、独自のジャンル「かわいいフューチャーベース×メタル」を打ち出したことで、国内外のリスナーから注目を集めるようになりました。とくに海外ファンとの交流は、「日本発の音楽で共感を得られることの喜び」を実感する機会となり、自分の音楽が誰かに届いているという感覚が、自己肯定感や表現の自信につながっていったそうです。
こうして、仕事と表現の両輪を通じて「自分のやりたいことは、“人に伝えること”“面白さを共有すること”なのだ」と明確に言語化できたことは、世良氏にとって大きな転機だったと語られました。「好きなことを続けることで、自分が見えてくる」。その言葉に、講義を聴いていた多くの学生たちも大きくうなずいていました。
自分の居場所 ― 掛け算が導くオリジナリティ
講義の後半では、世良氏が自身のキャリアにおいて抱えてきた葛藤と、そこから導き出された“自分らしさ”のあり方について語られました。
国内大手IT企業ではAIの専門家として、社内外のプロジェクトをリードする一方で、音楽ユニット「Neko Hacker」の活動も精力的に続けていた世良氏。しかし、いずれの分野にもその道を極めた「プロ」が多数存在するなかで、「自分は中途半端ではないか」「どちらでも突き抜けられないのではないか」と悩む時期があったといいます。
そんなとき、ふと気づいたのが「自分がプロフェッショナルとして突出していなくても、“掛け算”によって他にはない強みが生まれる」という考え方でした。
「データサイエンティスト × 音楽クリエイター」という一見異なる2つの軸をかけ合わせることで、同じAI技術を扱う専門家や、音楽を作るクリエイターの中でも、唯一無二の立ち位置を築けるのではないか。こうした気づきが、オリジナリティの源となり、「世良氏にしかできない価値」を生み出す原動力になったといいます。
たとえば、AIを活用した音楽ライブや、AIと人間の協調による作曲支援など、これまでにない新たな表現を生み出す場面では、まさにその“掛け算”の力が発揮されました。周囲からも、「世良さんに頼みたい」「このプロジェクトには世良さんが合っている」といった評価を得られるようになったことで、自分の“居場所”を感じられるようになったと振り返ります。
「プロでなくても、組み合わせ次第で、自分だけのポジションをつくることができる」。その言葉は、今まさに将来の方向性に悩む学生たちにとって、心に残るメッセージとなったようです。
2人の自分 ― 環境がつくる役割の違い
講義の終盤では、世良氏が「2つの仕事」を続ける中で抱えてきた“役割の違い”への戸惑いや、それをどう乗り越えてきたかについて語られました。
国内大手IT企業という組織の中では、データサイエンティストとしての専門性だけでなく、マネジメント業務やメンバーの育成にも携わる立場にある世良氏。プロジェクトの進行管理や周囲との調整といった「管理職としての自分」は、時に慎重さや冷静さが求められる役回りです。
一方で、「Neko Hacker」の音楽活動では、自由な発想で作品を生み出し、感情や個性を前面に出すクリエイターとしての側面が強くなります。ライブではファンと一緒に盛り上がり、SNSでは気軽なコミュニケーションも欠かしません。
このように、1人の中に“正反対の性質”を持つ2人の自分が存在しているように感じ、「自分は二重人格なのではないか」と悩んだ時期もあったそうです。
しかし、あるとき「人は環境によって役割が変わるもの。むしろ、異なる環境に応じて最適な自分を出せることは強みだ」と考え直すようになったといいます。それは、「どちらが本当の自分か」を問い詰めるのではなく、「どちらも自分である」と受け入れる転換でもありました。
たとえば、職場では論理性や計画性を重視し、チーム全体の成果を見据えた行動が求められます。一方で音楽活動では、直感や感情、個人的な“好き”を追求することが、作品の魅力につながります。そうした「環境ごとに異なる自分」を行き来することは、複数の価値観を行き来できる柔軟性を持っているという証でもあると、世良氏は語ります。
この話を通じて学生たちは、「環境によって自分が変わってしまう」と不安に思うのではなく、「その場に応じて自分の役割を柔軟に変えていけることこそが、これからの社会で求められる力なのだ」と気づかされたようでした。
自己実現 ― 2つの仕事の共通点とこれからの挑戦
講義の締めくくりでは、世良氏がこれまで歩んできたキャリアの集大成として、「AIと音楽」という一見かけ離れた2つの分野に、実は共通する本質があることに気づいたと語りました。
AIの仕事では、社会や人の課題に向き合い、その解決に向けて最適なモデルや技術を設計・提供します。そこには、相手のニーズを正しく理解し、それに応えるかたちでアウトプットを届けるという、強い「他者志向」があります。
一方で、音楽活動においても、「自分の好きなものを突き詰めて表現する」ことだけでなく、「どうすれば聴いてくれる人に届くか」「どんな表現が共感されるか」という問いを常に意識してきたといいます。つまり、音楽という“感性の仕事”においても、やはり「他者の存在」が中心にあるのだと気づいた瞬間があったのです。
「相手のことを思い浮かべながら、創造して、届ける」。それが、AIにも音楽にも共通する“ものづくり”の本質だと、世良氏は力強く語ります。これは、単なる技術力や表現力だけではたどり着けない、深いレベルでの自己理解と他者理解の融合です。
また、今後の展望として、世良氏は「この2つのキャリアをますます交差させ、誰かの生き方や学び方に新しい選択肢を提示していきたい」と語りました。AI×音楽という新しい表現のあり方や、パラレルキャリアという生き方そのものが、「既存の枠にとらわれずに生きる」ためのロールモデルになることを目指しているそうです。
学生たちは、このメッセージを真剣な表情で受け止めていました。「好きなことを続けていい」「掛け合わせることで新しい可能性が生まれる」「その先には、他者に貢献する喜びがある」。そのひとつひとつの言葉が、進路や将来に迷う彼らの背中をそっと押していたようでした。