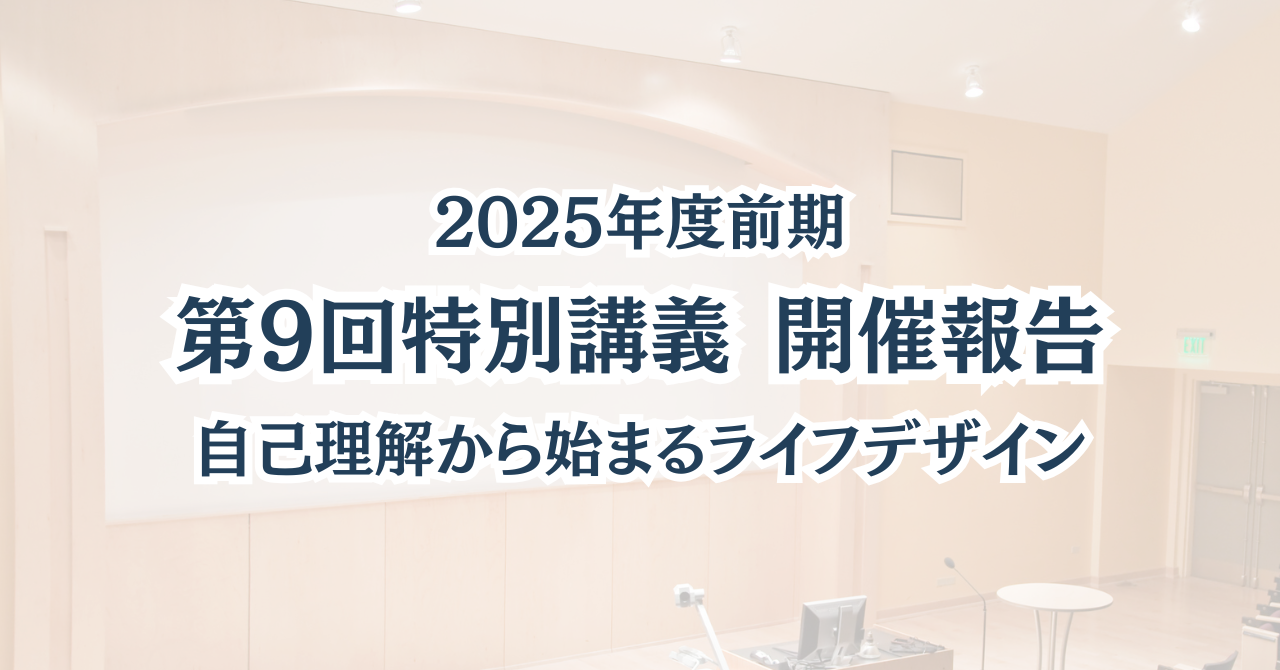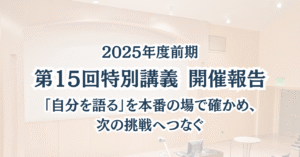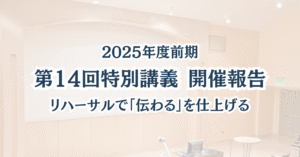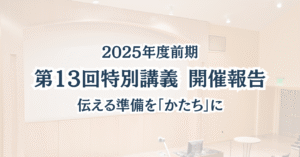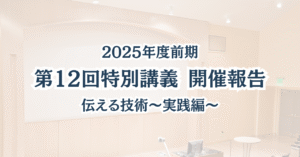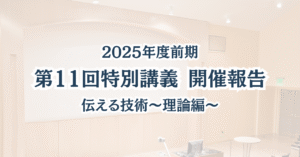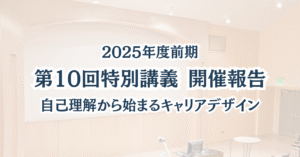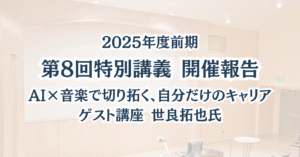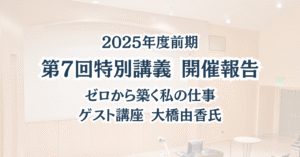高崎経済大学では、2025年度も「特別講義」シリーズを開講しており、全15回のうち第6回目の講義が6月3日2限目に実施されました。
本シリーズは、学生が「自分らしく生きる力」を育むことを目的としたプログラムであり、単なる知識の習得にとどまらず、思考・行動・対話のサイクルを通して深い自己理解と実践力を養うことを目指しています。
第6回目のテーマは「自己理解の深化と自己表現」
今回は、これまでの講義で掘り下げてきた“志”や“価値観”をもとに、いよいよ「自己理解した内容を人に伝える」という段階に踏み出しました。自分自身の“軸”を可視化したうえで、どのように相手に伝えるかという“表現”のフェーズに移行するための土台を築く時間となりました。
自己理解を“プレゼンテーション”へと接続する
今回の講義では、これまでのワークで深めてきた自己理解を、次なるステップである「自己表現」へとつなげていくという大きなテーマが提示されました。講師・野口は冒頭で、「単に自分を知るだけで終わるのではなく、自分という存在を誰かに伝える力を身につけてほしい」と語り、そのために「プレゼンテーション」という方法論を用いる意義を学生たちに示しました。
プレゼンテーションといっても、単に人前で話す技術を学ぶということではありません。野口は、「アニメや映画といった表現の世界では、作品を形にする前に“プロット”や“構成資料”と呼ばれる企画書のようなものを作成する」と紹介し、自己表現にも同様の準備が必要であることを強調しました。
すなわち、自分自身をひとつの“企画”として捉え、その企画書=自己理解のアウトプットを言語化する力が、社会に出てからは非常に重要になるということです。
講義では今後、「自分という企画の訴求ポイントはどこか」「誰に伝えるのか」「どのようなストーリーで語るのか」といった視点で、自分の特徴や経験を整理し、シナリオにまとめ、最終的にはプレゼンテーションに仕上げていくプロセスを学んでいきます。
これらのステップは、就職活動やOB・OG訪問といった“実践の場”でもそのまま応用できる実践的なスキルです。野口自身も「これは新人の頃に知りたかった」と振り返りながら、学生たちにとって今学ぶ価値が非常に高いものであると語りました。
講義の終盤では、「まずはプレゼンのことはいったん忘れて、今回は自己理解にしっかり集中して取り組んでほしい」としながらも、15回にわたるシリーズ全体としては「自己を理解し、それを人に伝えるまでを一貫して体験する」ことが目指されていると再確認されました。
ワーク① 自分の「大事なこと」を掘り下げる
―価値観を言語化し、人生の軸を見つけるために
講義前半では、自分が人生において何を「大事にしているか」を明らかにするワークが行われました。これは、今後「得意なこと」「好きなこと」と掛け合わせるための土台をつくる、非常に重要なプロセスとして位置づけられています。
学生たちはWebClassから配布された電子ワークシートを使いながら、あらかじめ提示された問いに対して自分の経験をもとに自由に記述を行っていきました。問いには、「尊敬する人は誰か」「影響を受けた出来事は何か」「社会に足りないと感じるものは何か」などが並び、自身の記憶や感情を丁寧に振り返る構成となっていました。
回答を重ねた後は、それらをグルーピング・抽象化し、「自分が大切にしている価値観」をいくつかのキーワードにまとめていきます。最終的には、それらの価値観をランキング化し、自分の中でどれが最も重要なのかを可視化するまでが1セットの流れでした。
このプロセスを通じて、学生たちは「自分がなぜ特定の行動を選ぶのか」「なぜあのときあの出来事に感動したのか」といった“行動や感情の背景”にある価値観を言語化することができるようになりました。
講義中には、グループでの共有の時間も設けられ、「尊敬する父の生き方が、自分の価値観の形成に深く影響していた」と語った学生の発表に、教室内から共感の声があがる場面もありました。
野口からは、「価値観というのは、人生や仕事のあらゆる選択の“基準”となるもの。自分の中にある“譲れないもの”を知ることが、未来の選択を楽にしてくれる」と語られ、学生たちはワークを通して“言語化することで力になる”という実感を得ていました。
ワーク② 「得意なこと」を言語化する
自己理解の後半では、「得意なこと」を言語化するワークが行われました。ここでの目的は、自分が「意識せずにできてしまうこと」「自然とやってしまっている行動」に目を向け、自分だけの“強みの種”を見つけ出すことにあります。
野口は冒頭で、「得意なことと好きなことは違う」と明確に定義しました。得意なこととは、意識しなくても無意識でできてしまう動作や習慣のこと。たとえば「気づいたら資料を作ってしまっていた」「人の話を聞いて自然とまとめていた」といった、本人が“特別なこと”だと思っていないような行動に、実は強みの本質が隠れているのです。
学生たちは、以下のような問いを手がかりに、自分の経験を振り返って書き出していきました:
- 人生で充実していた体験は?
- 周囲にイライラしたとき、その背景には何があるか?
- 人から「すごいね」と言われたことは?
- 大学を今辞めるとしたら、心残りになることは?
- 自分の長所を一言で表すとしたら?
回答が出にくい場合には、1000項目に及ぶ「得意動作リスト」も用意されており、それを眺めながら直感的にピンときた項目を選ぶというアプローチも紹介されました。
さらに、自分で書き出した「得意なこと」を「充実感の有無」「成果との結びつき」「確信の程度」に応じて分類する作業も行われ、自分の“得意”をより客観的に見つめ直す機会となりました。
ワーク中には、講師・野口自身の例として「パクリのプロ」としての特徴が紹介され、「優れた人の手法を瞬時に真似して、自分の力として発揮する」ことが自分の無意識的な強みだったという実例も共有されました。
最後には、得意なことの“使い方”にも注意が促されました。たとえば、同じ特徴であっても、それをどう使うかによって「長所」にも「短所」にもなるという考え方です。
野口は「特徴に善悪はない。それをどう捉えるかが大事」と語り、学生たちは自分の中にある“資源”を、よりポジティブに活かす視点を得ていました。
ワーク③ 「好きなこと」を掘り下げる
講義の終盤では、自己理解の3つ目の柱として「好きなこと」にフォーカスするワークが行われました。ここでは、自分の“気持ちが動く対象”や“夢中になれるもの”を言語化することを通じて、自分の内面にある情熱の源泉を探ります。
野口は、「好きなことは、得意なこととは異なり、つい意識してしまうもの」「“ドキドキする”“ずっと考えてしまう”ようなことがヒントになる」と説明しました。そして、自分でも気づいていなかった“好き”を掘り出すために、次のような問いが学生たちに投げかけられました:
- 人生で夢中になったことは?
- 思い出すとワクワクする瞬間は?
- 時間を忘れて続けられることは?
- 周囲に語りたくなることは?
- 子どもの頃から好きだったことは?
学生たちは、それぞれの問いに対し、自分の経験や日常を振り返りながら記述を進めました。また、参考として提示された「好きなことリスト」を活用し、自分の感情が動いたキーワードを選びながら、自分の“好き”の傾向を整理していきました。
このワークでは、単に言葉を並べるだけでなく、「自分の“好き”を他者に伝える」ためのトレーニングも含まれていました。グループワークでは、「書いた内容の中で、本当に心から“好きだ”と思えることを共有する」というミニ発表が行われ、学生たちは照れや恥ずかしさを感じながらも、互いの“好き”を認め合う温かな時間が流れていました。
なかには、「アニメが好きだけれど、周囲の目が気になって言いづらかった」「音楽について話すときは、自然と気持ちがこもる」といった学生の声もあり、自分の“好き”を肯定的に表現することの難しさと同時に、その大切さにも気づかされる場面となりました。
野口は、「好きなことは、ニッチであっても、堂々と語っていい。むしろ、それがあなたのオリジナリティであり、キャリアや表現の核になっていく」と語り、学生たちの背中を押しました。
また、「たくさん洗い出すことよりも、“これだ”と思えるものに出会うことが大切」との言葉に、多くの学生が深くうなずき、自分の内面に向き合う姿勢を改めて強めていました。
「好き」と「得意」を掛け合わせて未来を描く
今回の講義では、「大事なこと」「得意なこと」「好きなこと」の3つの自己理解の柱を洗い出すプロセスが完了し、次回以降はいよいよそれらを掛け合わせて“自分の志”や“仕事のあり方”へとつなげていくステージに進んでいきます。
野口は、「好き」と「得意」を掛け合わせることこそが、今後の社会において自分らしい働き方を見出す“戦略”になると力強く語りました。
「好きなこと、得意なこと、そのどちらか一方だけでは仕事や人生を長く続けていくことは難しい。掛け算で見えてくる“自分ならではの価値”こそが、これからの社会を生き抜くための武器になる」
という言葉には、多くの学生が真剣な表情でうなずいていました。
また、これから始まる後半の講義では、今回見つけた“自分の断片”を材料として、自分自身のシナリオを作り、それを人に伝えるためのプレゼンテーションスキルを学ぶことが予告されました。
その過程では、「企画書を書く」「構成を組み立てる」「相手に応じた伝え方を考える」といった、アニメ・映画・ビジネスプレゼンすべてに通じる“自己表現のための型”を実践的に学んでいく予定です。
野口からは、「プレゼンテーションとは、就職活動や面接のためだけのものではない。“自分は何者か”を他者に伝えるための、生きる力そのものだ」とのメッセージも共有されました。
講義の締めくくりでは、
「世の中が“知識をたくさん持っているかどうか”の競争から、“自分らしい価値を持っているかどうか”の競争に変わりつつある」
という野口の言葉が印象的に響き、自分を見つめることの意味をあらためて深く感じ取る時間となりました。
今回の講義で学生たちは、「自分が何を大切にし、何が得意で、何が好きなのか」を丁寧に言語化するという、極めて個人的でありながら普遍的な問いに向き合いました。
次回の講義では、それらをもとに「自分という企画」を構築し、実際に他者に向けて発信する力を育んでいきます。自己理解から自己表現への接続——。ここから、学生一人ひとりの“ストーリー”が本格的に動き出していきます。