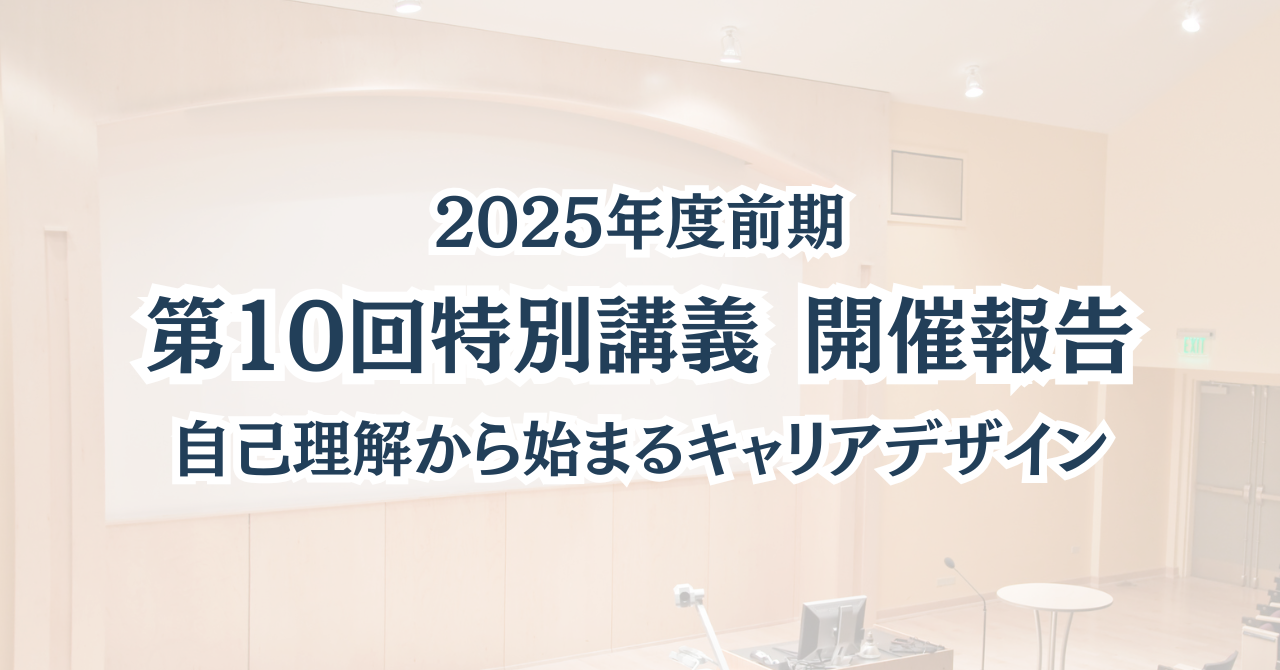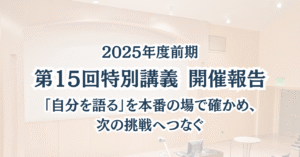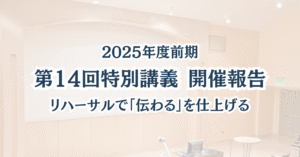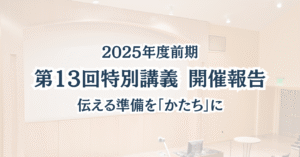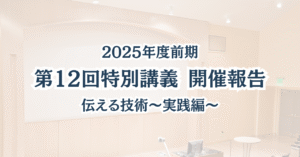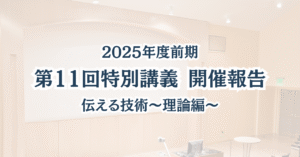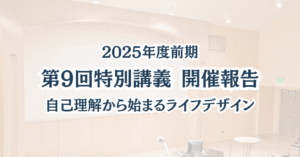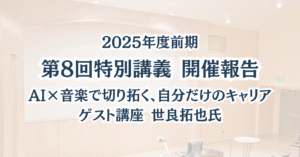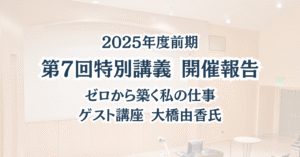高崎経済大学では、2025年度も「特別講義」シリーズを開講しており、全15回のうち第10回目の講義が6月24日 2限目に実施されました。
本シリーズは、学生が「自分らしく生きる力」を育むことを目的としたプログラムであり、単なる知識の習得にとどまらず、自己理解を深め、自らの志や価値観に基づいた行動をデザインしていく力を養うことを目指しています。
第6回目となる今回は、これまで扱ってきた「大事なこと」「得意なこと」「好きなこと」という3つの観点を整理し、それらを掛け合わせることで「自分らしい生業=仕事のタネ」を見出すためのワークに取り組みました。講義では、個人ワークと対話を通じて、学生一人ひとりが自分の可能性を多角的に捉え、社会との接点を探るプロセスが丁寧に展開されました。
3つの視点の棚卸し:「大事なこと」「得意なこと」「好きなこと」
講義の冒頭では、これまでに扱ってきた3つの重要な視点──「大事なこと」「得意なこと」「好きなこと」──について、改めて自分の中で整理しなおすワークが行われました。
まず講師・野口は、「今日のワークは、これら3つの視点を掛け合わせることで自分の“生業”を考える時間になる」と説明し、学生たちはそれぞれのワークシートを手に、再確認作業に入りました。
「大事なこと」の再確認
「大事なこと」については、過去の講義で作成したリストやピラミッドを見返しながら、改めて自分が何を大切にして生きているのかを振り返る時間が設けられました。
「大事なことは、最終的に人生の中で何を優先したいのかを判断する土台になる」と野口は語り、学生たちは「いつからその価値観が生まれたのか」「なぜその価値観が自分にとって重要なのか」といった問いと向き合いながら、自分自身の価値観を再構築していきました。
「得意なこと」の掘り起こし
「得意なこと」については、野口から以下のようなメッセージが送られました。
「得意なことは、自分では気づきにくい。なぜなら、それは“無意識にできてしまうこと”だからです」
学生たちは、周囲から「つい頼まれること」や「自分では当たり前にやっていること」を思い出しながら、ポジティブにもネガティブにもなりうる“自分の特徴”を書き出していきました。
たとえば、野口自身が「人をもてなすことが得意だったが、子どもの頃は『気を遣いすぎ』とネガティブに捉えられていた」というエピソードも紹介され、学生たちは「一見短所に見えることでも、見方を変えれば長所になりうる」という視点に気づかされていきました。
「好きなこと」の再確認
「好きなこと」については、前回の講義で取り組んだリストを見返しつつ、今回は“問いかけの時間”を省略して、既存のワークシートや補助資料を活用して自ら掘り起こす形式がとられました。
学生たちは、自分の検索履歴や日常の行動の中にある“関心の傾向”をヒントに、「何をしているときにワクワクするか」「時間を忘れるようなことは何か」といった観点から、自分の“好き”を丁寧に拾い上げていきました。
野口は、「得意かどうかは置いておいて、とにかく惹かれるもの」「意味がわからなくてもなぜか気になるもの」を大切にするよう促しました。
このように、講義の前半は、学生が「大事なこと」「得意なこと」「好きなこと」の3つの棚卸しを通じて、自己理解の解像度を高める時間となりました。それぞれの項目には15分の時間がしっかり確保され、学生は集中して自分自身と向き合うことができるよう工夫されていました。
掛け合わせワーク:「好きなこと」×「得意なこと」
3つのリストの棚卸しを終えた学生たちは、いよいよ本講義の中核となる「掛け合わせワーク」に取り組みました。ここでは、「好きなこと」と「得意なこと」を掛け合わせることで、“本当にやりたいこと”の予備リストを発想していくことが目的とされました。
講師の実体験から学ぶ「掛け合わせの意味」
野口はまず、自身のキャリアの例を用いながら、好きなことと得意なことの掛け合わせによって仕事の形がどう変わるかを解説しました。
たとえば、野口はITやテクノロジー、ビジネスが「好き」だったため、システムエンジニアという職業を選びました。しかし、プログラミングのような“作る作業”はあまり得意ではなく、次第に苦しくなっていったといいます。
一方で、「記憶に残る説明をする」「人前で魅力的に語る」といった能力は「得意なこと」だったため、それを掛け合わせることで、「生成AIエバンジェリスト」や「プレゼンテーション講師」という、自分に合った新たなキャリアにたどり着いたという実例が紹介されました。
このエピソードを通じて、学生たちは「好きなことを仕事にする」だけでなく、「得意なことをかけ合わせる」視点の重要性を実感していきました。
ワーク:好き×得意から仕事を発想する
続いて学生たちは、自身の「好きなこと」と「得意なこと」のリストを掛け合わせ、そこから生まれる可能性を自由にリストアップしていきました。
野口からは、「初めは具体的な職業名でなくてもよい。どんな活動か、どんな場面か、どんな役割か、といったレベルでも構わない」という説明があり、学生たちは手元のワークシートに次々とキーワードを書き込んでいきました。
さらに、「うまく思いつかない場合は、“ずるいな”と感じた誰かを思い出すのもヒントになる」とのアドバイスもありました。「あの人、あんなことで評価されていてずるいな」という感情の裏には、「自分もそれに近いことができる(=得意)」「自分もやってみたい(=好き)」という感情が潜んでいることがあるからです。
学生たちは個人ワークの時間(約20分)を使ってじっくり掛け算を行い、その後、周囲の学生と「こういうの思いついたけど、どう思う?」と話し合いながら、発想をさらに深めていきました。
「“話を聞くのが好き”と“分析が得意”を掛けたら、“インタビュアー”や“カウンセラー”が浮かんだ」
「“文章を書くのが得意”と“ファッションが好き”で、“スタイリングに関するコラムを書く”というのが見えた」
「“盛り上げ役が得意”と“アニメが好き”から、“イベント司会”や“声優イベントの進行”が出てきた」
このように、掛け合わせによって初めて見えてくる“新しい自分”を発見する学生が多く、自分の特性を組み合わせることで職業イメージが一気に広がる様子が印象的でした。
それは“仕事”か“趣味”か?:社会とつながる視点
「好きなこと」と「得意なこと」を掛け合わせて発想した“やりたいことリスト”が出揃ったところで、講義は次のステップへと進みました。
それは、「それは誰かの役に立つか?」「感謝されるか?」「社会とつながっているか?」という、“フォー・ユー(for you)”の視点で、自分のやりたいことを見つめ直すフェーズです。
趣味か、仕事か。それを見分ける問い
野口は、「得意×好きで出てきたアイデアのすべてが仕事になるとは限らない」とした上で、次のように話しました。
「人に喜ばれないとダメということではありません。自分のための活動は“趣味”として、人生を豊かにする力になります」
「一方で、誰かが求めてくれて、それに対して感謝されたり、お金を払ってくれるとすれば、それは“仕事”に近づいていく可能性があります」
このように、「誰かに必要とされているか」という社会的視点を加えることで、学生たちは「仕事」としてのリアリティを持って自分の掛け算結果を見直す時間を持ちました。
最後のワーク:「仕事」としてブラッシュアップ
掛け算によって見えてきたやりたいことが、「誰かにとって価値のあることなのか」を検討するワークが5分間実施されました。
学生たちはそれぞれのリストをもとに、「これは自分の内面的欲求だけで生まれたものなのか?」「誰かに喜ばれる未来が想像できるか?」と自問自答しながら、リストの中で“仕事寄り”のものと“趣味寄り”のものを分類したり、補足メモを加えていきました。
野口は、「この区別が今の時点では曖昧でも構わない。むしろ『どんな視点が足りなかったか』に気づくことが今日のゴール」と伝え、学生たちの思考を深掘りする視点として以下のような例を挙げました。
- もし、今の掛け算で“仕事っぽいもの”が思いつかないなら、
→「そのために足りない情報は?」「世の中にはどんな仕事があるか?」をリサーチする意識を持つこと。 - 逆に、思いついたが不安なら、
→「実際にそれをしている人は?」「どうやって仕事になっているか?」を観察してみること。
このようにして、講義では“生業”というテーマを一足飛びに定義するのではなく、あくまで「仮説」として柔らかく持ち帰ることが大切であると強調されました。
講師からのまとめと学生へのメッセージ
講義の最後には、講師・野口から学生に向けて、キャリア形成における本質的な姿勢とメッセージが語られました。
まず野口は、自身の過去のキャリアの変遷を振り返りながら、「好きなこと」「得意なこと」を掛け合わせて仕事をつくることの“難しさ”と“可能性”について、以下のように率直に語りました。
「僕は、35歳でようやく“自分に合った仕事”にたどり着いた」
「それまでに10個近く仮説を立てて、実際にやってみて、違うと感じて、を繰り返した」
「最初から“正解”を探す必要はない。まずは“これかもしれない”という仮説を持ち、動いてみること」
そして、今回の講義で学生が取り組んだ「好き×得意」の掛け算もまた、「仮説づくりの第一歩」であると位置づけられました。
加えて、野口は「自己理解だけでなく、今後は“他者に伝える”技術が必要になる」と話し、次回以降の講義ではプレゼンテーションの力を育てる内容へと進んでいくことが示されました。
「自分を知ったら、次はそれを人に伝える。言語化できてこそ、誰かとの接点が生まれる」
「だから来週からは、“伝える力”をテーマに、プレゼンテーションの技術を学んでいきます」
このメッセージとともに、学生たちは本講義の締めくくりとして、自身の考えを「誰かに伝える」ことへの意識を高めながら、次のフェーズへと進む準備を整えていきました。