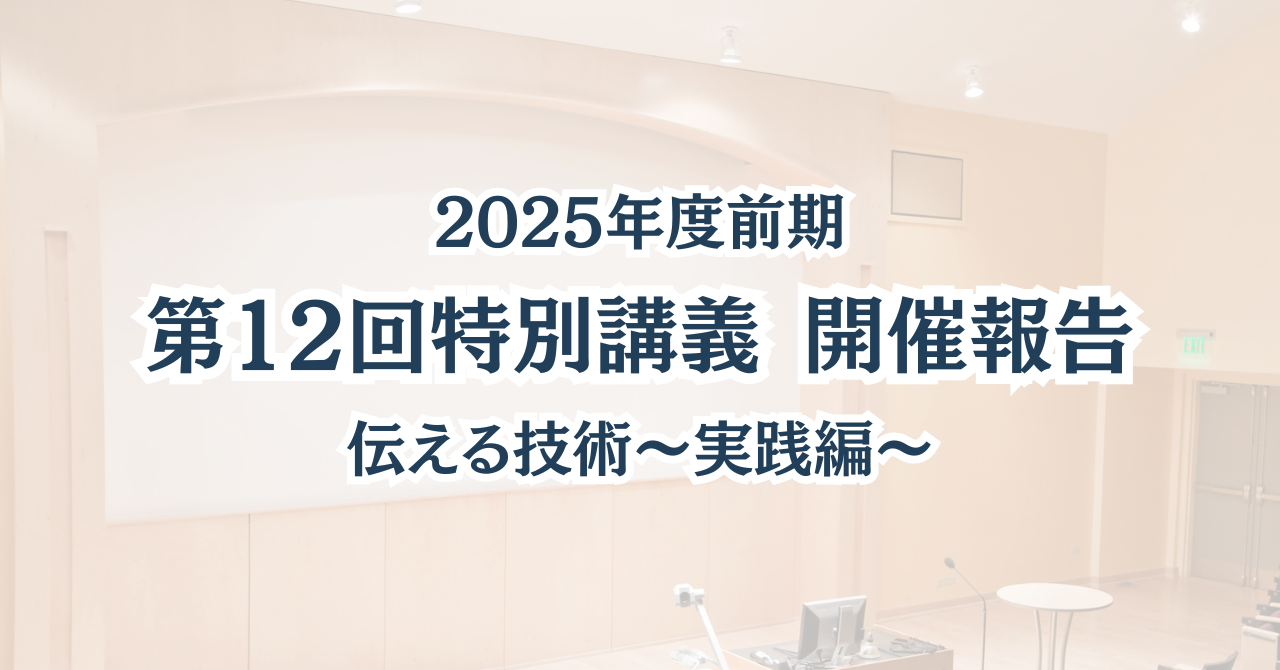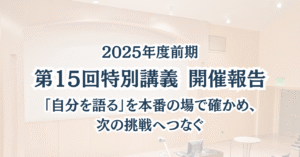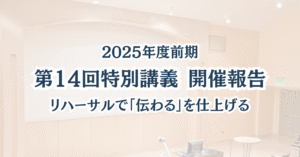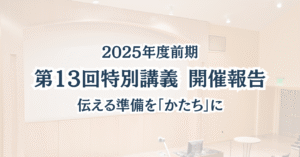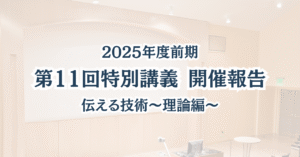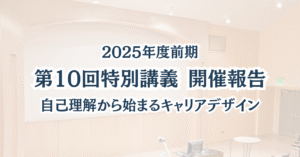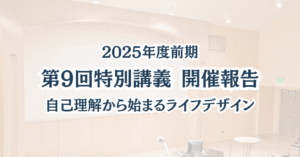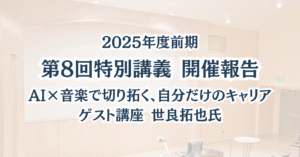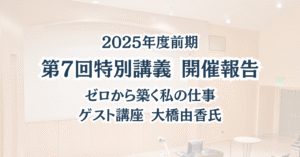高崎経済大学「特別講義」シリーズの第12回は、前回までに扱った“伝わる”ための基礎(緊張対策・聞く耳の条件・構造/ことば/話し方)を踏まえ、「企画を立てる→構造を選ぶ→台本(シナリオ)を書く」という実践工程に踏み込みました。
野口は、最終プレゼンを「修正版まで仕上げ、聴衆から感想・助言を受ける場」にするビジョンを共有。当初「残り5回」と触れたのち、配当の再確認を行い、残り3回で「台本完成→練習&修正→本番発表・評価」という流れで進める旨を伝えました。
目次
企画の第一歩:「企画とは何か」を定義し直す
野口はまず、企画=「あることをするための計画や目論見」という素朴な定義を提示。定義は平易でも、いきなり良い企画は立てにくい。だからこそ、うまくやっている人の“やる順番”を真似るところから始めると強調しました。
最初に考えるべき順番:誰のため?(ターゲット)→目的→手段
チーム討議からの出発点
- 学生からはAs-Is(現状把握)や目的の明確化といった重要観点が挙がりました。
- 野口の結論:「最初は“誰のために”から始める」。
多くの人が“自分ができること(手段)”から考え始めて迷子になる。相手(ターゲット)を具体化してはじめて、目的・やり方・提供内容がブレなくなる。
“誰”が決まったら:WHY→HOW→WHAT(ゴールデンサークル)
- ターゲット確定後は、
- WHY(なぜやるか/目的)
- HOW(どうやるか/方法)
- WHAT(何を提供するか/成果物・コンテンツ)
の順で落とし込む。
- 例示として、若者への価値提供を考えるケースを想定。目的を「新しい層を獲得するために、説明的でなく印象的・魅力的に伝える力をつける」等に据え、HOWは“インプレッシブに伝える技術の習得”、WHATは“具体的なプレゼン手法・コンテンツ”といった形で連鎖させていきました。
参考事例①:社内番組(DX事業の理解促進)
- 背景:社長の“DX事業”方針が現場に浸透せず「それって何?」状態。
- ターゲット:まず“売ってくれる人”=営業部門。
- キャンペーン:「わかったフリ、やめよう」をスローガンに、分かったフリを禁じ、分かるまで腹落ちする文化を醸成。
- アセット整備:構造化ナレッジ、すぐ使える資料群、Q&A等を番組と連動で提供。
- 結果(講義内共有ベース):4年目に突入、昼休み帯の社内番組ながら4万回規模の視聴が積み上がるなど、継続と浸透の基盤に。
参考事例②:テレビ東京コラボ番組の企画
- 構成:パックン×野口×有識者の三者で解説するビジネス系コンテンツ。スポンサー枠でありながら、200万再生を獲得(講義内共有)。
- テレ東側の提案書:出演体制や配信プラットフォーム、視聴者層データ等が提示される。
- 自社側の設計:自社の狙い(例:DX事業の推進)に沿って、誰/目的/方法/提供物を自社視点で再構成。経営層に届くか等、ターゲットと接点の濃さを吟味して実装しました。
ワーク①:企画書ドラフト(個人→共有)
- 配布フォーマット(誰/目的/HOW/WHAT)を使って、まずは個人で15分集中。
- その後、20~25分の想定で仕上げ、さらに45分かけてチーム内で共有・助言。
- 野口は巡回し、詰まった箇所に伴走。
- “WHOで詰まる”ときの処方:
「誰かの問題を解決する」「誰かを喜ばせる」の二軸で考えると突破口が掴みやすい。 - テーマの補足:本演習のテーマは基本「自分」。ただし練習段階としては自分に関わるテーマ(例:就活の自己PR/恩人への感謝など)に広げても可。
- “WHOで詰まる”ときの処方:
共有された好例
- 学生Aより(IT系インターン)
- ターゲット:業務効率系Web/Windowsアプリを扱うIT企業の面接官。
- 目的:採用したいと思わせる/育てれば使えそう/すぐ辞めなさそう――と評価軸を分解。
- コンテンツ:独学で作ったアプリ実例。
- 野口の所見:ターゲットの具体化の深さと目的の粒度の細かさが秀逸。伝えるべき内容が自ずと定まる好設計。
- 講師・石川より(エンタメ企画)
- ターゲット:アイドルマーケットの10代~20代。
- メッセージ/コンテンツ:「会いに行けるアイドル」を成立させる仕掛け(握手会や投票等)。
- 野口の所見:著名プロデューサーの設計にも通じるWHY→HOW→WHATの積層が明確。フレームで語れることを体感できる例。
ワーク②:構造を選ぶ(三幕構成×プロットの型)
野口は、「起承転結」は説明向き、「三幕構成」は惹きつけ向きと整理。短時間プレゼンで活きる三幕=オープニング(引き込み)/ボディ(展開)/クロージング(結び)をベースに、以下のようなプロットの型を紹介しました。
- 例)設定→奮闘→解決策
- 例)現状→理想→新しい世界
- 例)別離→移行→再出発 ほか
ガイドライン例(抜粋)
- オープニング:現状やギャップ、問いで期待感を醸成。
- ボディ:根拠・エピソード・仕組み等で理解を積み上げる。
- クロージング:示唆・呼びかけ・ビジョンで行動に接続。
※エレベーターピッチの「結論先出し」も手だが、今回の演習では惹き込み→理解→行動喚起の基本動線を重視。
台本化(スクリプト化)の手順
- 型を一つ選ぶ(上記のいずれか)。
- ガイド文に沿って、各幕の要素を文章に起こす。
- 言葉は“声にする前提”で書く(言い切り/短文/固有名詞/数字/比喩の使い分け)。
野口のデモ・プロット:「母に伝える『もう大丈夫』」
- 選んだ型:別離→移行→再出発。
- 狙い:就職を機に、母に「もう安心して自分の人生を楽しんで」と伝える。
- オープニング(別離):大学時代のだらだらした朝から一変、社会人初日のアラーム音、慣れないネクタイ、満員電車。
- ボディ(移行):入社式で刺さった言葉――「君たちはお客様ではありません。あなたは何を価値提供しますか」。受け身から価値提供者へ発想が転回。
- クロージング(再出発):家に戻ると、台所から唐揚げと味噌汁の匂い。守られてきた日々への感謝を口にし、「給料日、奢るからね」。小さな決意が胸に宿る。
→ 目的に対し、具体の情景・象徴語で感情曲線を描くプロット例として提示されました。
実施上の難しさと次回の支援
- 受講生のつまずき:
- プロット選定に迷う/文章が出てこない/動画的な演出イメージと口頭の台本の違いで混乱…など。
- 野口は、次回は言葉ベースの台本サンプル(ベストプラクティス)を複数用意し、参照しながら書けるよう支援すると案内しました。
これからの進行(残り3回)
- 次回(第13回):企画と台本を本格作成(構造完成+一通りのセリフ化まで)。
- 次々回(第14回):声に出しての練習/相互フィードバック/修正。
- 最終回(第15回):本番プレゼン(修正版で発表)と評価。
まとめ:今日の学びと次回への宿題
- 順番がすべて:誰のため→WHY→HOW→WHAT。
- 構造が骨格:三幕構成で「惹き込み→理解→行動」。
- 台本は声前提:短く言い切る、数字・固有名詞で具体に、比喩や情景で感情線を描く。
- 演習の肝:まずは1つの型でよい。ガイドに沿って1幕分だけでも文章化してみる。
次回は、今日の企画ドラフトを土台に台本を完成させます。チームでの読み合わせに向け、オープニングの“つかみ”だけでも書き切ることを各自の最低ラインの宿題としました。野口は、「修正版で本番へ」というゴールを見据え、実戦的に使える設計図(企画)と脚本(台本)を、教室全体で磨き上げていく姿勢を改めて示しました。