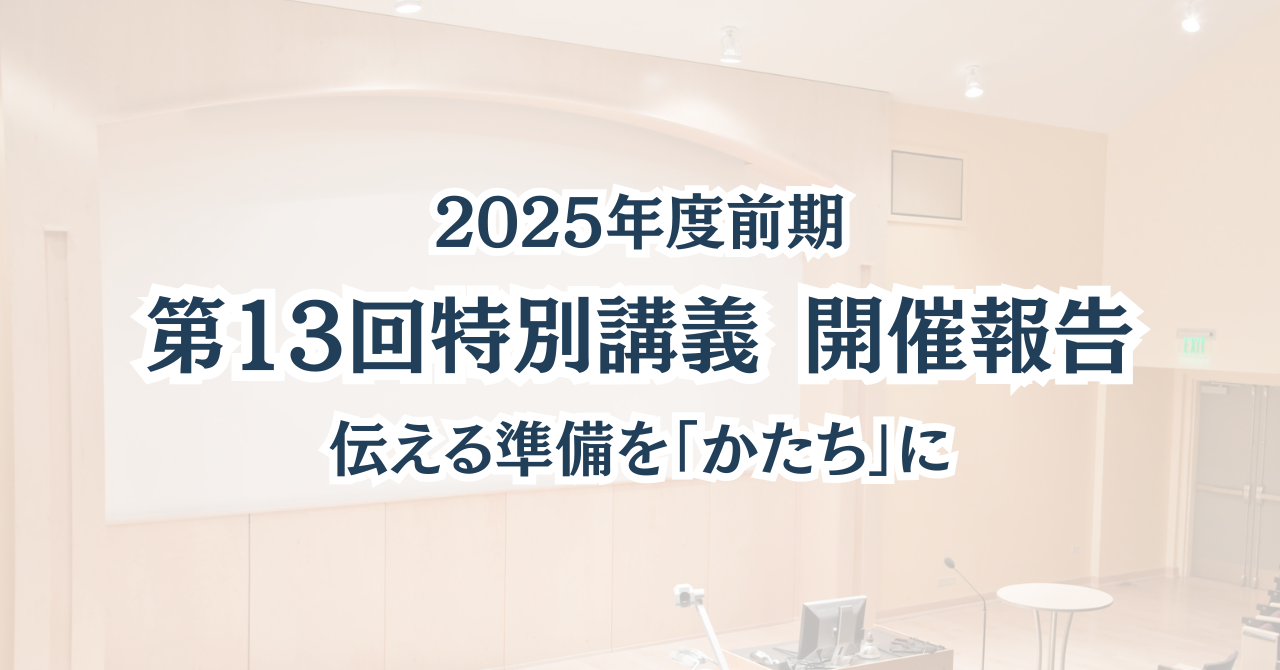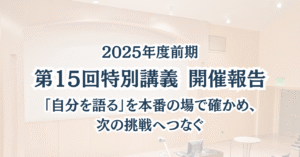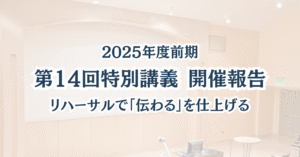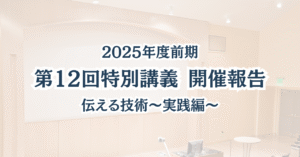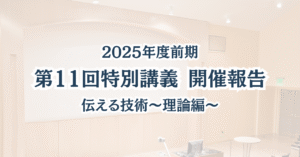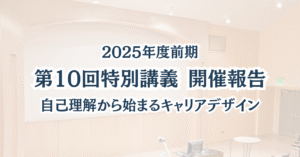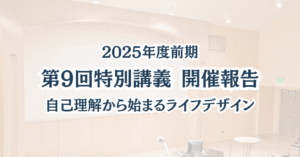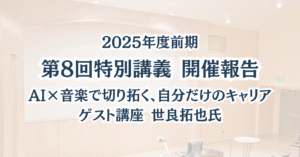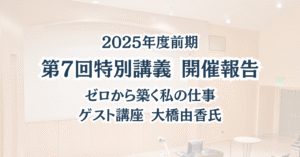高崎経済大学では、2025年度も「特別講義」シリーズを開講しており、全15回のうち第13回の講義が実施されました。本シリーズは、学生が「自分らしく生きる力」を育むことを目的としたプログラムであり、単なる知識の習得にとどまらず、思考・行動・対話のサイクルを通して深い自己理解と実践力を養うことを目指しています。
第13回のテーマは、最終発表に向けた「企画書・台本づくり」です。これまでに培ってきた“大事なこと・好きなこと・得意なこと”という自己理解を土台に、誰に/何のために/何を伝えるかを明確化し、三幕構成などのストーリー設計を意識しながら実際に口にする言葉まで落とし込む実践に取り組みました。
雨天にもかかわらず多くの受講生が集まり、活気ある雰囲気のなかで授業が始まりました。
第13回のゴール——企画書と台本をつくる
本時の目的は明確です。
- 企画書:誰に、何のために、何を伝えるかを定義し、素材(自分の経験・価値観・エピソード)を整理して設計する。
- 台本:採用する構成(例:三幕構成など)に沿って、実際に口にする言葉まで落とし込む。声のトーン・音量・テンポの指示も書き込む。
「やり方」自体は前回までにレクチャー済みのため、きょうは手を動かして書く時間をたっぷり確保。ワーク中心の講義となりました。
企画書テンプレートと“ケース”の選択肢
迷いやすい受講生のために、電子ファイルには参考ケースが用意されています(使わなくても可)。代表例は次のとおり。
- ケース1:自分の個性と志を3分で語る(学内発表のシーン想定)。目的例:聞き手の“決意スイッチ”を入れる。
- ケース2:自分が取り組みたい社会課題をテーマにプレゼン(公開の場や社会人向けイベント想定)。目的例:課題の説得力ある可視化と、行動喚起。
- ケース3:就活・インターン等の自己紹介(グループ面接のシーン想定)。目的:合格。聴き手=面接官。
実務的アドバイス
- ケース3を選ぶなら、志望業界・組織を具体的に仮置き(例:市役所/県庁/省庁/企業など)。
- 募集要項や“求める人物像”を一瞥し、訴求軸(強み・姿勢)を合わせる。
- 先に“誰に・何のために”を固定しないと、内容は定まらない。
台本づくりの骨格と記述のコツ
野口は、映画やコンテンツ制作にも通底する三幕構成などのストーリーテンプレートを、プレゼンの骨格として活用する意義を解説しました。台本には、声の高さ・大きさ、間、テンポなどの演出指示も書き込みます。なお、文字数の目安は次のとおりです。
- 約3分=900字前後
- 約2分=600字前後
書いたら声に出して読むことで、文語と話し言葉のズレや冗長さに気づけます。
授業の中盤、実際の発表の様子を想像してもらうため、講師2名によるデモンストレーションが行われました。
デモンストレーション①:講師・溝渕(就活向け自己紹介)
最初の実演は、面接官が目の前にいる想定での自己PR。訴求軸は「適応力・柔軟性」。
- 背景:大学2年時のアイルランド交換留学。日常の前提が通じない経験(バス停で手を挙げないと停まらない/シャワーの操作に戸惑う など)を通じ、自分の常識を相対化。
- 展開:日本語学習者のコミュニティに参加・支援側へ回り、SNS発信を開始。肯定的な反応を得て「自分の役割」を見いだす。
- 結論:変化の大きい現場でも、前向きに行動して成果に結びつけられる——という具体的価値の宣言。
解説ポイント:構成は「別離→移行→再出発」。
- 以前の自分や前提からの“別離”
- 異文化での試行錯誤という“移行”
- 見出した強みで相手組織にどう貢献するかという“再出発”
この型は自己紹介・自己PRに汎用性が高く、書きやすいフレームとして紹介されました。
デモンストレーション②:講師・石川(価値観を揺さぶる導入)
二つ目の実演は、挑発的な問いかけで始まるスピーチ。
- 解凍:「皆さんどうぞ人生を諦めてください…」という極端な言い回しで受け手の前提に揺らぎを与える。
- 変化:“一流大学か否か”は人生の価値とは無関係で、志と行動こそがカギだと新しい方向を提示。社会の中でやりがいを持って働く人がごく少数だという数字紹介もあり、聴き手に「自分はどう生きたいか」を突きつける。
- 再凍結:個性を信じ、必要とされる場に接続し続けることを促すメッセージ。
解説ポイント:構成は「解凍→変化→再凍結」。
相手が持っている信念に揺らぎを与えてから新しい行動の喚起を促している点で力強いスピーチとなっています。
このスピーチは「特別講義の受講生」に向けて設計されていたため、受け手の没入感に差が出ました。ここから、ターゲット設計の精度が伝達力に直結することが実感的に共有されました。
書き進める際の実践ヒント
- 最初に“誰に・何のために”を固定。迷う場合は、志望組織の面接官など、具体的な聴き手を即決する。
- 素材は自分の事実ベース(経験・観察・感情)。抽象論よりも、固有名詞と具体描写が説得力を生む。
- 物語構成は手段。型に囚われすぎず、相手の感情と行動の変化を主眼に。
- 冒頭は“問いかけ”も有効。聞き手の脳をこちらに向ける。
- 声出しチェックで違和感を早期発見。冗長な箇所は削り、キーメッセージを前倒しに。
個人ワーク:55分の集中タイムと宿題の位置づけ
本時は55分の個人ワークで、企画書→台本の順に作成。進捗が出た人は、読み上げて微修正まで実施しました。
次回は調整時間(約15~20分)を設けたうえで、練習に入ります。
まとめ——仕上げの3回で“伝わる”を作る
第13回は、これまでの自己理解を“他者に届くかたち”に編集するための実務回でした。企画書で設計し、台本で言葉にする——この二段構えこそが、最終発表を成功させる鍵です。次回は微修正と練習、本番は第15回。ターゲットと目的を明確に、自分の事実を核に、声に出して研磨していきましょう。