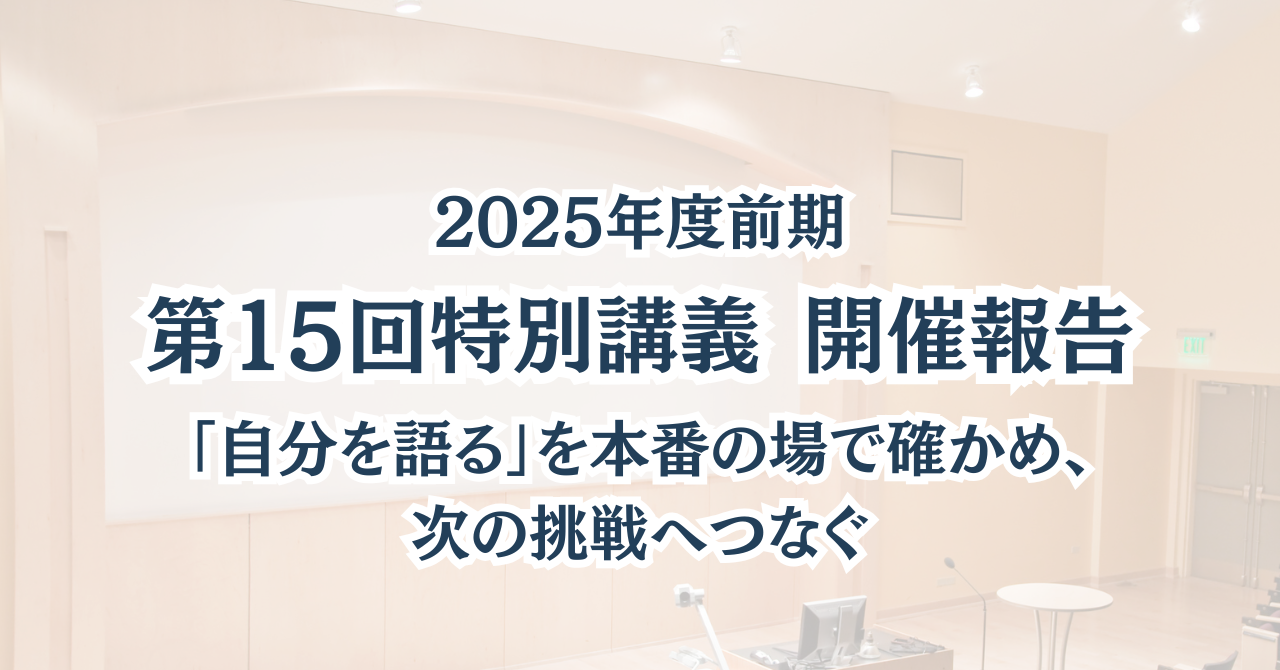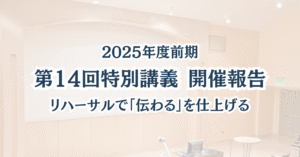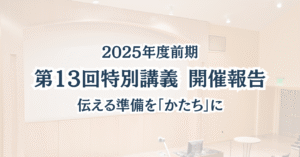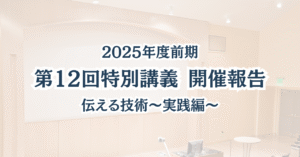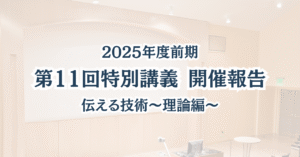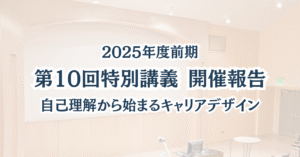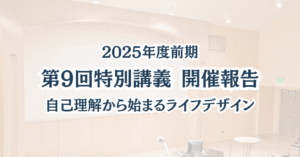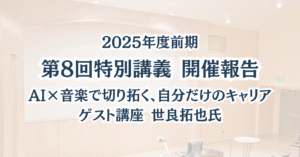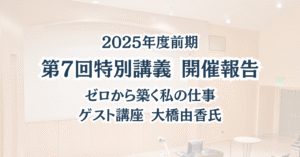高崎経済大学では、2025年度も「特別講義」シリーズを開講しており、全15回のうち第15回(最終回)が実施されました。本シリーズは、学生が「自分らしく生きる力」を育むことを目的としたプログラムであり、単なる知識の習得にとどまらず、思考・行動・対話のサイクルを通して深い自己理解と実践力を養うことを目指しています。
最終回の本講義は、第14回での練習とフィードバックを土台にした“最終発表”。各自が磨き上げてきた企画書と台本(自己紹介スピーチ)を、教室という本番の場で発表し合いました。
授業の前半|各チームごとに最終発表を実施
授業は冒頭、4名程度のチーム単位での最終発表から開始。これまで作成してきた内容をもとに、1分の企画説明(誰に/何を/なぜ/どうやって)+3分スピーチを基本フォーマットとして発表しました。
- 空間の使い方:前方ステージや通路を自由に活用し、一歩踏み出す/一拍置くといった動きで緊張と緩和をつくり、聴衆の集中を誘導。
- 伝達設計:目線の配り(対角線への視線移動)、声の“高さ”と“大きさ”の使い分け、意図的な「間」の配置など、第14回での指摘点を各自が反映。
- 運営:共通タイマーで進行し、拍手で区切って次の登壇者へ。所感共有は簡潔に留め、最終回にふさわしいテンポで全員発表を完了しました。
野口は、「読み上げに固執せず、伝える相手を見て話す」ことを再確認。音声化したときに現れる“息継ぎ位置・語尾・冗長さ”が前回より明確に整っている点を評価しました。
代表発表①|学生・Kさん「挑戦×自信」
前半での発表の後、2名の学生が代表して発表を行いました。
1人目は学生のKさん。メッセージは「自信は行動の中で生まれる」
- ターゲット:高校生・大学生(進路や将来に不安がある層)
- 目的:挑戦の価値を伝え、自己と向き合うきっかけを与える
- 訴求メッセージ:「自信は行動の中で生まれる」
- コンテンツ:①英会話教室での気づき ②英語発表会での成長 ③挑戦で得たもの
本編では、「間違えてもいいから口に出して話す」という先生の言葉を起点に、発表会で完璧さより“伝えたい意志”が評価軸になることを実感したプロセスを、臨場感ある描写で展開。
結びでは、「最初の一歩が自分を変える」と聴衆に呼びかけ、会場は大きな拍手に包まれました。野口は、声の低域と速度のコントロールによって要所が立ち上がった点を高く評価しました。
代表発表②|学生・Sさん「目標設定と自己理解」
2人目の代表はSさん。メッセージは「目標設計が成長を加速させる」でした。
- ターゲット:クラスの皆さん
- 目的:体験を踏まえ、目標設定と自己理解の必要性を伝える
- 訴求メッセージ:「目標設定と自己理解は、自分を成長させる」
- コンテンツ:高校時代の後悔/入学前の再設計/実践と成果
高校時代、流されて進路を選んだ後悔を直視し、入学前に恩師と短期・中期・長期の目標を設計。
1年次には学習と応募を重ね、全国大会の最終審査進出・全国紙掲載という成果へ。要所で間を置いて感情を届ける語りが印象的で、三幕構成の起伏も明確でした。
最後は、「自分をよく知り、言葉にし、期限を切る」という実装ポイントで締め、力強い拍手が送られました。
野口は、第14回での練習・FBを受けて“ものが変わった”とコメント。発声・構成・間の使い方が総合的に向上したことを全体の学びとして共有しました。
「ムーブメント」を起こす力|最初のフォロワーになる勇気
講義の最後には、講師の石川より、学生に向けて力強いメッセージがありました。
石川は、社会が動く瞬間を説明するために、TEDで知られる「How to Start a Movement」の例を取り上げ、「最初の一人が注目されがちだが、二人目(最初のフォロワー)が加わった瞬間に“孤立した行為”は“合図のある行動”へと変わり、場の空気が反転する」と述べました。
続けて、ムーブメント成立におけるキーファクターを以下のように整理しました。
- 最初のフォロワーの役割:先行者の隣に立ち、同じ行為を可視化して伝播の“安全信号”を出す存在。
- 合図の具体化:拍手、うなずき、同調行為(模倣)など、周囲に「ここに乗って良い」という明確なシグナルを送る行動。
- 転換点の構造:2人→3人→4人…と閾値を越えると、「参加しない理由を探す場」から「乗り遅れたくない場」へと規範が変わる。
石川はまた、自身の経験として、野口の新たな試みが立ち上がった初期に「最初のフォロワーとして隣に立った」ことを紹介。結果として二者の取り組みが仕組み化され、学内外の活動へ波及した経緯を共有しました。
最後に「全員がリーダーである必要はないが、誰もが“最初のフォロワー”にはなれる」とし、良い動きに気づいたときは最初に手を挙げる/拍手する/真似るといった小さな行為が場を変えると強調し、学生にエールを送りました。
学長メッセージ
学長は本講義の位置づけを「大学は知識の倉庫ではなく、人生を設計する工房である」と端的に表現し、スタンフォード大学の実践に触れながらライフデザインを先に持ち、その設計図をもって授業という資源を主体的に使う重要性を示した。教育目的については次の二点を明確化しました。
- 学生本人の力を伸ばすこと:自ら考え、選び、動く力を涵養する。
- 社会を良くする人材を送り出すこと:仕組みを作り、ムーブメントを起こす担い手を育てる
大学の学びを自分の設計に活かす主体性、そして社会にムーブメントを起こす人材として羽ばたいてほしい——そんな力強いメッセージで学長の話は締めくくられました。
クロージング|「自分を語る」から、次の一歩へ
第15回は、第14回の練習・FBを確かな土台として臨んだ“最終発表”の日。
学生Kさんの「自信は行動の中で生まれる」、Sさんの「目標設定と自己理解が成長を加速させる」という核は、15回の学びを象徴していました。
ここからは、自分の言葉で自分を語り続けること、そして良い動きに最初のフォロワーとして加わる勇気を携え、各自の次のフィールドへ。全員の健闘を称え、シリーズは温かな拍手で幕を閉じました。