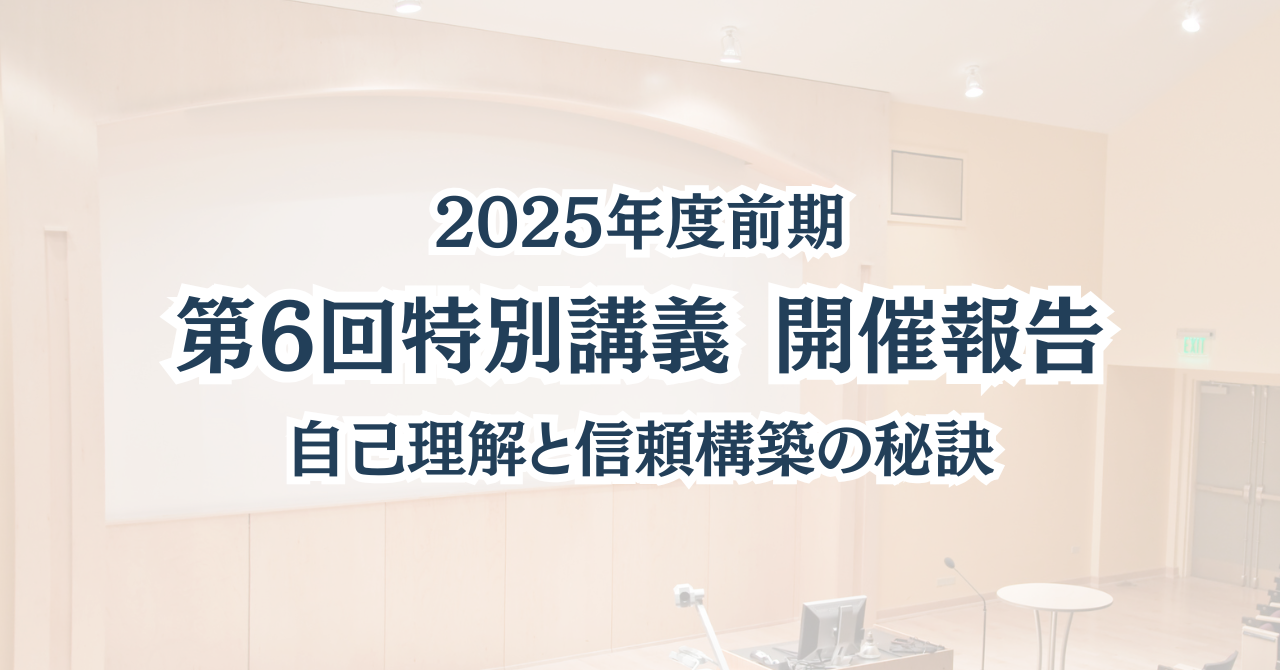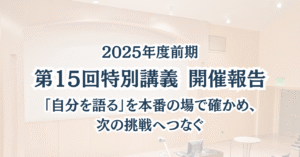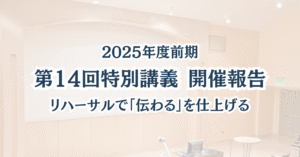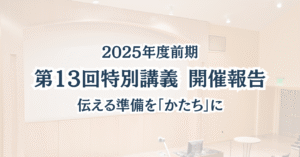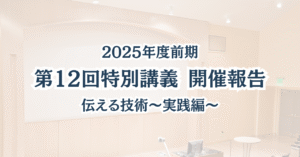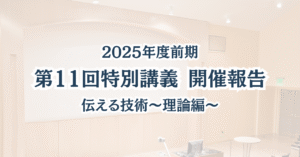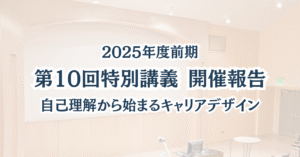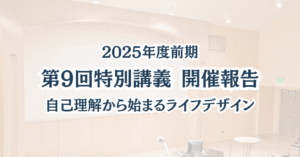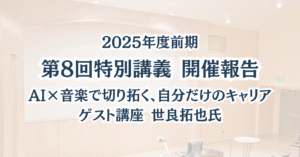高崎経済大学では、2025年度も「特別講義」シリーズを開講しており、全15回を通じて学生が「自分らしく生きる力」を育むことを目指した学びが展開されています。知識の習得にとどまらず、自己理解・内省・対話・実践というプロセスを通じて、学生たち一人ひとりが将来のキャリアや人生に主体的に向き合う力を育てていきます。
第6回目となる今回の講義は、「自己認識と信頼構築の秘訣」と題され、「得意なこと」「好きなこと」といった個人の資質や関心に焦点を当てる内容となりました。
これまでの講義で扱ってきた「志」や「価値観」に加え、「得意」や「好き」といった領域に目を向けることで、学生が自らの“強み”や“生き方”をより深く理解し、社会とのつながりの中でどのように信頼を築いていけるかを探る時間となりました。
本講義では、講師自身のリアルなストーリーを通じて、自己理解のプロセスを実感的に学ぶ機会が提供され、学生たちは多くの気づきと共に、自分自身と向き合うきっかけを得ることができました。
講義のテーマと背景
この講義の背景にあるのは、「信頼される人間になるにはどうすればよいのか?」という問いです。ただ努力するのではなく、「自分らしさを活かした信頼の築き方」を探ることが、今回の中心的な目的でした。
講義では、まず“信頼”という言葉の構造を資本という観点から読み解くフレームが紹介されました。これは、ビジネス書などでも注目されている「ウェルビーイング(幸福)を構成する3つの資本」──すなわち、
- 時間資本(自分が持つ時間)
- 人的資本(知識・スキル)
- 社会資本(人とのつながり・信頼)
という視点を用いたものです。
学生たちはこのフレームを通じて、単に「勉強すればよい」「就職すればよい」といった短期的な視点を超えて、「自分の人生をどう戦略的に構築するか」を問い直されました。
「時間をどこに投下するか」「何を得意とし、どんな信頼を築くか」──こうした問いに向き合うことは、社会に出る前段階にある大学生にとって極めて重要です。
また、今回の講義では、長年苦手な仕事に従事しながらも、自分の“得意”と“好き”を再発見し、信頼を築きながらキャリアを転換させていった講師・石川自身のストーリーが中心に語られました。そのリアルな語りは、学生たちに「今すぐ答えが出なくても、問い続けていい」という勇気を与える内容となりました。
このように、第6回講義は「個性」と「社会性」の接点に焦点を当てながら、学生一人ひとりが“自分らしく生きる土台”を築くための重要なステップとなりました。
好きなことは「結果」ではなく「原動力」
講義の冒頭、講師の石川は自身の大学時代を振り返り、「自分の中で唯一持っていた価値観は、“好きなことをして生きていきたい”という思いだった」と語りかけました。これは、学生時代から一貫して自身の生き方を形作る中核にあった考えであり、講義全体の土台となるメッセージでした。
石川は当時、好きなことを仕事にすれば、自然とエネルギーが湧き、夢中で取り組めるようになる。結果として、努力が積み重なり、人よりも成果を出すことができる。そうすれば評価され、報酬や信頼につながり、より豊かな人生が築けるはずだ、という自分なりの“人生の成功ロジック”を描いていたと明かしました。
しかし一方で、学生にとって「好きなこと」を明確に言葉にするのは難しいという現実も踏まえ、「好きなことは、最初から明確に持っていなければならない“結果”ではなく、自分の行動の“原動力”として探っていくもの」だと強調しました。
石川自身も、かつては「自分に本当に好きなことがあるのか」と戸惑い、迷いながら模索を続けていたといいます。その体験を踏まえた上で、「好きなことの見つけ方」について、具体的な問いを通じて学生に考えるきっかけを提供しました。
「本棚にどんなジャンルの本が並んでいるか?」
「どんな言葉に反応してしまうか?」
「いま、お金を払ってでも学びたいと思うことはあるか?」
こうした質問を通じて、自分の内面に潜む関心や興味に目を向ける時間が設けられました。単なる“職業の好き嫌い”ではなく、「気づけば気になってしまうこと」「無意識に反応してしまうこと」といった、より深層的な“好き”を掘り下げる試みです。
講義のこのセクションでは、「好きなこと」を明確な答えとして求めるのではなく、日常に潜む“ざわざわ”や“ひっかかり”を手がかりに、自分の感性と向き合う姿勢が促されました。それは、今後の進路やキャリア形成だけでなく、自分らしい生き方を選び取るうえでの大切な出発点となる問いかけでもありました。
得意は無意識の中に眠っている
講義の中盤では、「得意なこととは何か?」という問いが投げかけられました。石川は「得意なこととは、無意識にやってしまっている“動作”や“思考のクセ”の中にある」と語り、学生たちにとって意外な角度からの自己理解を促しました。
このセッションではまず、「最近イラっとしたこと、ざわざわしたことは何か?」を出発点に、自身の行動パターンや反応に目を向けるワークが行われました。というのも、人は自分が無意識に“当たり前にできること”に対して、他人がうまくできていない場面に直面すると、心がざわついたり、イライラしたりすることがあるためです。そこにこそ、「自分にとって自然にできる=得意なこと」が隠れているという視点が示されました。
石川は自身の例として、「イベントの司会がうまく進行できていないと、自然とざわざわしてしまう」と語り、それが自分にとっての得意な動作=“場を整え、盛り上げること”であると気づいたと述べました。こうした気づきは、単に「うまくできること」という表層的な理解ではなく、「無意識にやってしまうこと」「やらずにはいられないこと」としての“深層の得意”を捉えるものでした。
また、学生たちには、さまざまな「得意動作リスト」が共有されました。たとえば、
- 無意識に人をまとめてしまう
- 他者のモチベーションを引き出してしまう
- 新しいアイデアを統合してしまう
- とにかく人を公平に扱ってしまう
- 納得するまで考えてしまう
- ルールを守りたくなってしまう
といった動作例が挙げられ、「こんなことは得意とは言えない」と思っていたことが、実は自分にとっての強みである可能性があることを認識する時間となりました。
学生同士のシェアタイムも設けられ、「自分では当たり前すぎて意識していなかったことが、他人から見るとすごいことだった」といった気づきが各所で生まれていきました。
このセクションを通して、石川は「得意なこととは、意識して努力してできるようになったものではなく、既に備わっている無意識の才能である」と強調し、学生たちに自分の行動の“当たり前”を疑う視点を提供しました。
自分の得意は、案外「自分では取るに足らないと思っていた動作」の中に眠っている。そんな発見が、学生たちの自己理解を一層深める契機となった講義パートでした。
講師自身のリアルな物語から得た学び
講義の後半では、石川自身が歩んできたキャリアと人生の紆余曲折が、率直に語られました。学生時代は「好きなことを仕事にしたい」という強い思いを抱きながらも、社会に出てからは思い描いていたような職業に就くことはできず、結果的に18年間、「自分が苦手とすること」を中心とした仕事に従事していたといいます。
その間、2度のうつ病を経験し、自己肯定感、家族や職場からの信頼、経済的な安定を一時的にすべて失った過去も包み隠さず語られました。39歳のときには、「社会から取り残されたような感覚」に陥っていたといいます。
そんな状況の中で転機となったのが、NEC社内のイベントで出会った同僚・野口圭の存在でした。講師として登壇していた野口の姿に心を大きく揺さぶられ、「この人のそばで働きたい」「エネルギーのある人と一緒に何かをしたい」と直感的に感じたことが、環境を変えるきっかけとなりました。
加えて、休日に「好きなことだけはやってみよう」と始めたバスケットボールのコーチ活動では、自分が得意とする「場を盛り上げる力」「個性を見極めて伸ばす力」が自然と発揮され、そこから思いもよらず「信頼」や「感謝」の声を得る体験につながっていったといいます。
さらに、かつての営業時代の上司から「営業としては評価しづらかったが、職場を盛り上げる力は突出していた」と語られたエピソードも紹介されました。それは、石川自身が「自分の得意は“本業”ではなかった部分にあった」と気づく大きな契機になったといいます。
この一連のエピソードを通して、学生たちは「苦手なことの中に身を置いたからこそ、得意なことが浮き彫りになる」という逆説的な事実や、「人との出会いが人生を変えることもある」という現実に触れ、自分自身の未来にもつながるヒントを受け取っている様子が見られました。
石川は、「“信頼される人間になる”とは、約束を守るような“守り”の信頼だけでなく、自分の得意を生かして、誰かの役に立つことを通じて“攻め”の信頼を得ることもある」と語り、学生一人ひとりが自分の持つ個性を再評価するきっかけとなるよう、熱意を込めて講義を締めくくりました。
好き・得意・大事なことの“交差点”を探す
講義の終盤では、「好きなこと」「得意なこと」「大事にしたい価値観」という3つの要素を掛け合わせるワークが行われました。石川は、「この3つの“交差点”に、自分が社会の中で活躍できる場所のヒントがある」と語り、学生たちにとって将来を描く上での実践的なフレームワークを提示しました。
具体的には、次のような構造です:
- なぜやるのか(価値観)
- 何をやるのか(好きなこと)
- どうやってやるのか(得意なこと)
たとえば「人の命を救いたい」という価値観を持ち、「医療に興味がある」「人と丁寧に接するのが得意」という人がいたとき、その人にとっての適職は“医者”という職業名そのものではなく、「人と信頼関係を築く医療現場」での役割であるというように、単なる職種ではなく、「どのように価値を実現したいか」の視点で自己を捉えることの大切さが示されました。
学生たちはワークシートを用いて、「自分が気になってしまうこと」「反応してしまうキーワード」「本棚に並ぶ本のジャンル」などから好きなことを探り、同時に「無意識にやってしまう動作」「他人の言動にざわつくポイント」から得意なことを見出し、前回の講義で考えた「大事にしたい価値観」と合わせて記述していきました。
また、石川は自身の例として、
- 大事なこと: 個性を生かして、楽しく生きること
- 好きなこと: ライフデザインや人が幸せに生きる方法を考えること
- 得意なこと: 場を盛り上げながら人の魅力を伝えること
を挙げた上で、「自分は、人の個性を見極め、才能へと昇華させ、豊かな人生を歩む人を増やしたい。そのために教育エンタメという形で新たな価値を届けたい」と語り、これらの要素が現在の活動につながっていることを説明しました。
このワークを通じて学生たちは、「将来何になりたいか」ではなく、「どのように生きていきたいか」「どのように社会と関わりたいか」といった視点から、自分自身の道を探る第一歩を踏み出しました。
まとめ:変化のきっかけは、自分を知ることから
今回の講義では、「好きなこと」「得意なこと」「大事にしたいこと」という、普段は曖昧に捉えがちな要素を丁寧に掘り下げ、それらをつなぐことで「自分らしい行動の原点」を見つけ出すプロセスが丁寧に導かれました。
特に学生にとって印象的だったのは、石川が自身の“うつ”の経験をはじめ、信頼を失った時期、そして再び信頼とエネルギーを取り戻していった過程を、飾らずに語った姿でした。そのリアルな語りは、学生たちにとって単なる“成功談”ではなく、「どんな状況にあっても、自分の中の種に気づき、整えることから再出発できる」という現実的な希望を感じさせるものだったと言えるでしょう。
学生たちからは、
- 「自分の中に“得意”や“好き”があると初めて思えた」
- 「好きなことが職業になるかどうかではなく、自分の価値観とつながっているかが大事だと気づいた」
- 「“自分には何もない”と思っていたけれど、無意識にやっていた行動に意味があると知った」
といった声が寄せられ、講義を通して「自分を知ること」そのものが、行動への第一歩となることを実感する時間となりました。
本講義は、自己分析やキャリア形成のための理論を伝えるだけでなく、講師の実体験を通して、「自分の言葉で語る力」「人生を自分で選び取る感覚」を学生たちに育む貴重な機会となりました。
特別講義シリーズは、今後も「志の育成」「行動のデザイン」「キャリアとの接続」といったテーマを軸に、学生一人ひとりが自分の人生を主体的に描けるよう、多角的な視点からの学びを提供していく予定です。