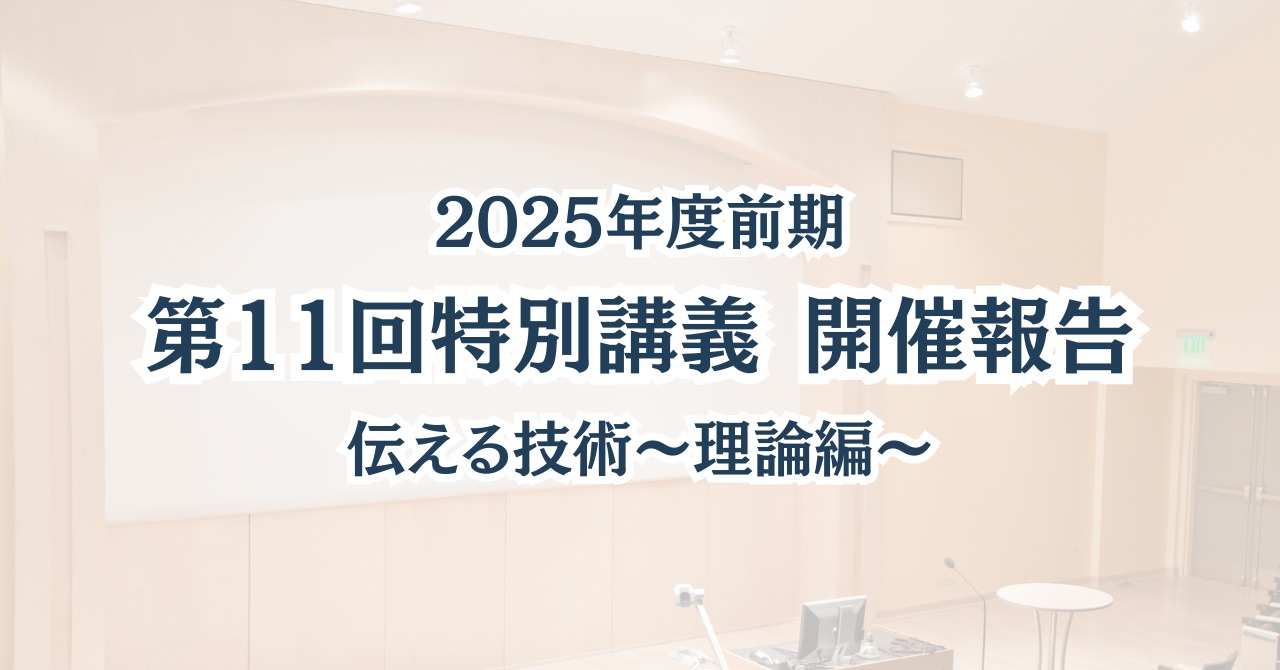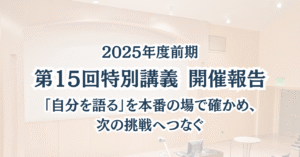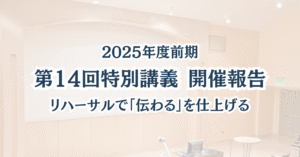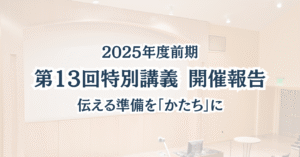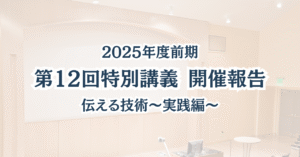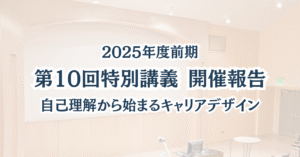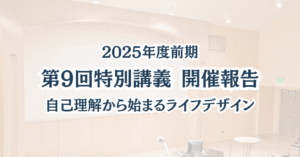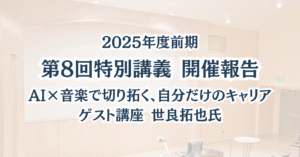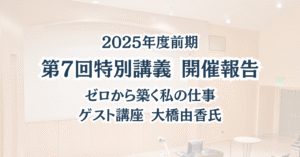高崎経済大学では、2025年度も「特別講義」シリーズを開講しており、本講義は全15回のうち第11回目として実施されました。今回のテーマは「伝える技術~心を掴むプレゼンをするには?~」。自己理解を土台に、実際に“伝える”場で成果を出すための実践的なハウツー(テクニック)に焦点が当てられました。
講義のねらいと全体構成
野口は、次回以降に予定する「自分の物語(自己表現)を組み立て、語る」実演に向けて、今回は“その手前の技術”を徹底的に磨く回だと位置づけました。ねらいは大きく三つです。
- 緊張をほぐし、平常心で話せる状態をつくる。
- 相手が“聞く耳”を持ち、内容が“伝わる”ための条件を理解する。
- 構成・ことば・話し方(デリバリー)の三位一体で、心を動かすプレゼンに近づく。
冒頭、教室は「オープンなコミュニケーション」を合言葉に、5分で4人チームをその場で編成。以降のディスカッションや次回の実演発表の基盤となる“仲間作り”からスタートしました。座席も前方へ詰め、互いが顔を見やすい配置に変更。初対面同士でも遠慮なく声をかけ合う空気が醸成されました。
1. プレゼンの目的は「態度変容」
野口は「プレゼンの目的は“話すこと”そのものではなく、相手の態度や行動が変わること」と強調しました。営業なら購買行動、学内なら理解や参加、就活なら評価や採用意志――いずれも“相手が動くかどうか”が成否を分けます。
緊張は「慣れていない」から起きる
大人数の前に立つと、視野は狭まり、身体はこわばります。なぜか――人は未知に出会うと緊張するから。
野口は緊張の正体を「人見知り/場所見知り/自分見知り」の三つに整理。
- 人見知り:初対面の人の前では固くなる。
- 場所見知り:初会場・初舞台はそれだけで負荷。
- 自分見知り:発表者としての“自分の状態”に慣れていない。
対策は慣れること。早めの会場入り、袖からの観客観察、入退場やスライド操作の通し稽古、本番同等の声量での読み上げ練習など、“未知”を減らすほど緊張は下がり、普段の自分を出せるようになります。緊張は0%にはならないが、必要な集中を残しつつ、固まりを防ぐのが現実的な目標とされました。
2. 「聞く耳」を得る4条件 ― なぜ今・なぜあなた・なぜ私
相手の心を掴むには、その前段に三段階がある――野口はこう提示しました。
① 聞く耳を持ってもらう → ② 伝わる → ③ 心が動く。
第一段階の鍵は、次の4条件を満たすことです。
- なぜ重要か(その話題の本質的価値)
- なぜ今か(タイミングの妥当性)
- なぜ私からか(話し手の資格・蓄積・現場性)
- なぜあなたが聞くべきか(聴き手にとっての意味・利得)
この4つが揃うほど、聴衆は「この話は自分事だ」と認識し、自然に耳を傾けます。野口は、実務でこの原則を“集客・告知”にも応用してきた具体例を紹介。知名度がない状態から2時間で300席を完売させた際、内容の価値には自信があった一方で「知名度」が不足していたため、社内要職者の推薦コメントを前面に掲出して“瞬間的な信頼”を補いました。足りない要素を見極め、4条件のどれをどう補強するかを設計する思考が重要だと説きました。
3. 「伝わる」ための三位一体:構造 × ことば × 話し方
(1) 構造:三幕構成で“引き込み→展開→結び”
人を物語に没入させる古典的な設計思想を、ビジネスや自己紹介に短く移植するのがコツ。
- 第一幕:期待や驚きを生む“つかみ”(問い/ギャップ提示/問題提起)
- 第二幕:証拠・事例・メカニズムで“理解”を積み上げる
- 第三幕:示唆・行動提案・ビジョンで“結ぶ”
面接での成功談や映画脚本の理論(例:解凍‐変化‐再凍結の枠組み)にも触れつつ、「起承転結」は説明向き、「三幕構成」は惹きつけ向きと位置づけました。次回の実演では、この型を使って各自の台本を作成していきます。
(2) ことば:受け手タイプ(VAK)に合わせる
人にはおおむね視覚/聴覚/体感覚の理解傾向があり、タイプにより刺さる表現が変わります。
- 視覚:図解・フロー・グラフ、語彙は「見える/描く/映る」
- 聴覚:論旨の筋道・用語の正確さ・数字の整列、語彙は「聞こえる/響く」
- 体感覚:感情・身体感覚・比喩、語彙は「重い/しっくり来る/ざわつく」
資料作りも表(聴覚)かグラフ(視覚)か、体験導入(体感覚)かで最適化が異なります。会話が噛み合わないときは「相手のチャンネルはどれか?」と仮説を立て、語彙・提示方法を合わせることが有効です。
(3) 話し方(デリバリー):トーン × ボリューム × テンポ × 間
- トーン(高低):開始は高めで明るさとエネルギー、重みを出す場面は低めで落ち着きを。
- ボリューム(大小):大は支配・届かせるため、小は注意喚起・メリハリのため。
- テンポ(速慢):導入はゆっくり=安心と理解を促進、要点は適度に加速=集中を喚起。
- 間:最強の無音。要諦前後の静寂がメッセージを耳と心に刻む。
これらを意図して使い分けると、「同じ内容でも伝わり方が変わる」ことを実演とともに体感しました。
4. 仕上げ:心を掴むための最後の条件
ここまでで聞く耳を獲得し、伝わる設計・運びが整っても、なお決定打になるとき/ならないときがある――野口が挙げた最後の条件は、「自分がその内容に心から掴まれているか」でした。
- 考えているか(Think):自分の頭で妥当性を検証しているか
- 言っているか(Say):口に出し、言い切れているか
- やっているか(Do):行動として体現できているか
- 感じているか(Feel):腹落ちし、感情が伴っているか
この四つが揃うと、言葉は熱と信頼を帯び、聴き手の感情に届きます。とりわけ「感じているか」は難所。野口は、花鳥風月に象徴される日常の感受性――季節の光や風、喜びやざわめき――を丁寧に味わうことが、感じる力の土壌になると示しました。
5. 参加型の対話と小ワークの要点
講義中はチームごとの1~2分ディスカッションを何度も挟み、
- どうすれば心を掴めるか
- なぜ人は緊張するのか、どう慣れるか
- 聞く耳を得る4条件を自分たちの場面に当てはめると?
- 300人集客を自分だったらどう設計するか
- 「伝わる」ための具体策(構造/ことば/話し方)
を自分事として検討。短時間でも考える→言語化→共有→フィードバックの循環を重ねました。終盤には1分の振り返りも実施し、印象や疑問をチームで言葉にすることで“学びの定着”を図りました。
まとめ
- 目的は態度変容。その前段として「聞く耳→伝わる→心が動く」の三段階がある。
- 緊張の正体は“未知”。人・場所・自分に“慣れる”設計で、平常心を確保する。
- 聞く耳の4条件(なぜ重要/なぜ今/なぜ私/なぜあなた)を満たし、足りない要素は設計で補う。
- 伝わる三位一体=構造(三幕)× ことば(VAK)× 話し方(トーン/ボリューム/テンポ/間)。
- Think–Say–Do–Feelを揃え、自分が掴まれている内容だけが相手をも掴む。
野口は、プレゼン技術を“人生のコミュニケーション”全般に効く基盤スキルとして提示しました。受講生は、次回の実演に向けて、設計された練習(慣れ)と台本化(構造化)を進めます。学んだ技術を仲間と磨き合い、自分の物語を、相手が動きたくなる形で語る準備が本格化していきます。