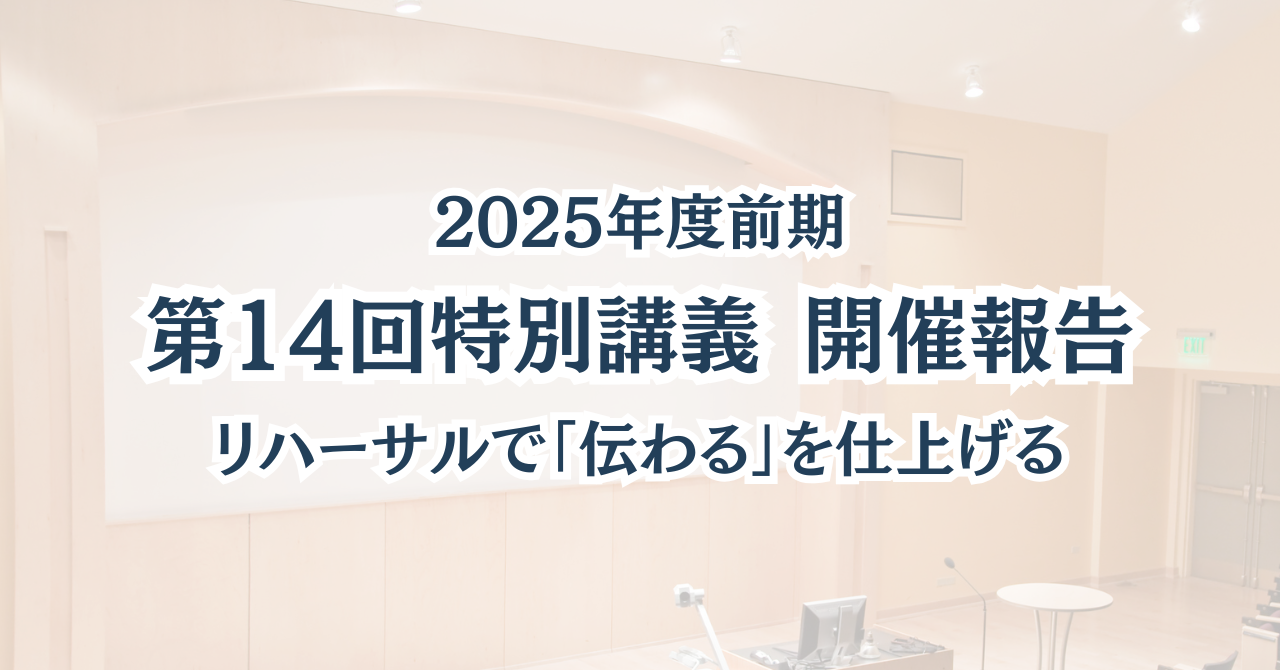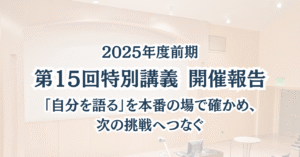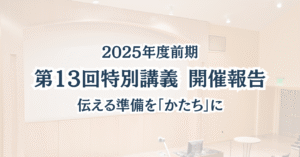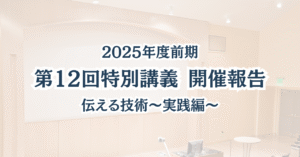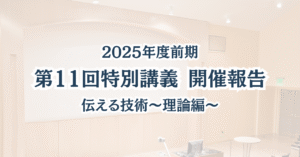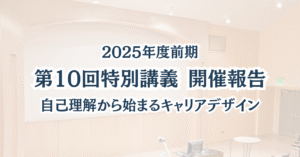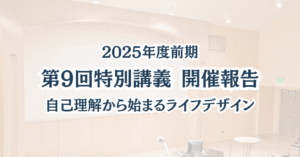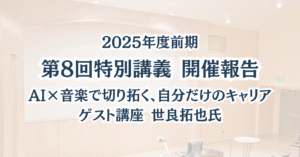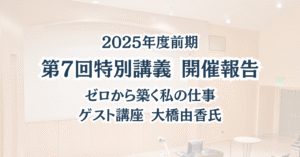高崎経済大学では、2025年度も「特別講義」シリーズを開講しており、全15回のうち第14回目の講義が実施されました。本シリーズは、学生が「自分らしく生きる力」を育むことを目的としたプログラムであり、単なる知識の習得にとどまらず、思考・行動・対話のサイクルを通して深い自己理解と実践力を養っていくことを目指しています。
第14回は、これまで各自が作り上げてきた自己表現の原稿(企画書・台本)を再点検・修正し、授業後半で発表のリハーサルを実施して相互にフィードバックを受ける、いわば本番直前の仕上げ回として位置づけられました。
当日の流れ(前半→後半の二部構成)
- 前半:原稿のブラッシュアップ
前回までの下地をもとに、表現の核(伝えたい一点)を再確認しつつ、言い回し・構成・強調点を調整。 - 後半:発表リハーサルとフィードバック
実際に短時間の発表を行い、聴き手から良かった点を中心としたフィードバックを受ける循環を回しました。
前半|原稿の最終修正——「声に出して整える」
野口は、仕上げ段階での最重要ポイントとして”声に出す”最終確認を強調しました。頭の中では滑らかでも、口に出すと句読点の置き所、語尾の単調さ、冗長さが明確になります。
修正では、次の観点をガイドに進めました。
- 伝えたい一点の明確化:読み手・聴き手に残したいメッセージを一句に圧縮。
- 構成の締め直し:冒頭で期待をつくり、本文で核を立て、結びで背中を押す三段運びを意識。
- 強調の設計:どの語を太く、どこで“間”を置くかをあらかじめ指定。
- 言い換え・削り:同義反復や装飾を削ぎ、可読より可聴を優先。
野口はまた、完成度の手応えが2~3割でも正常であること、練習しながら整える進め方を推奨。完璧主義に陥らず、まずは「通す→気づく→直す」の循環を回すよう促しました。
後半|発表リハーサル——実戦で“伝わり方”を検証
授業後半は、短時間の発表リハーサルを実施。各自が準備した台本をもとに実際に発話し、聴き手からフィードバックを受ける流れで進みました。ここでは、読み上げに固執せず、聴衆の反応を取り込みながら意味を立てる姿勢を重視しました。
練習の進め方(5分×人数のラウンド制)
各チームは順番を決め、1人あたり5分でローテーションします。
- 企画説明(1分)
企画書をベースに「誰に/何を/なぜ/どうやって」を要約。聴き手がテーマと狙いを素早く掴めるよう、情報は圧縮して提示。 - スピーチ(3分)
台本をもとに発話。ただし読み上げに固執しない。聴き手の反応を取り込みながら、強調語と間で意味を立てる実戦モード。 - フィードバック(1分)
左隣の人が「良かった点のみ」を即時に伝達。拍手で区切り、共通タイマーの合図で次の発表者へスムーズに移行。
補足ルール
・聴衆は相づち・うなずきで発表者を支える。
・フィードバックはポジティブ限定(改善指摘はこの回では扱わない)。
・声量はもう一段階大きく。間は恐れず置く。
共有タイム:やってみて分かったこと
練習後は各チームで感想交換を実施し、全体共有では次の声が上がりました。
- 「いざ話すと、頭の中のイメージと違った」
→ 野口は、発話によって自己の客観視が自然に起こると捉え、だからこそ口に出す練習が重要と評価しました。音声化で初めて見える粗密が、以後の推敲を後押しします。 - 「同じ授業を受けてきた仲間でも、新しい一面が見えた」
→ 3分という尺は“作り込みには短く、即興には長い”絶妙ライン。自分を掘り下げた者ほど核が立ち、聴き手の理解が進むことが確認されました。
第14回は、原稿の精度と発話の精度を結び付ける実戦の場となりました。次回はいよいよ最終回。これまで積み上げた自己理解と表現設計を、「伝わる3分」として社会に開く機会となります。